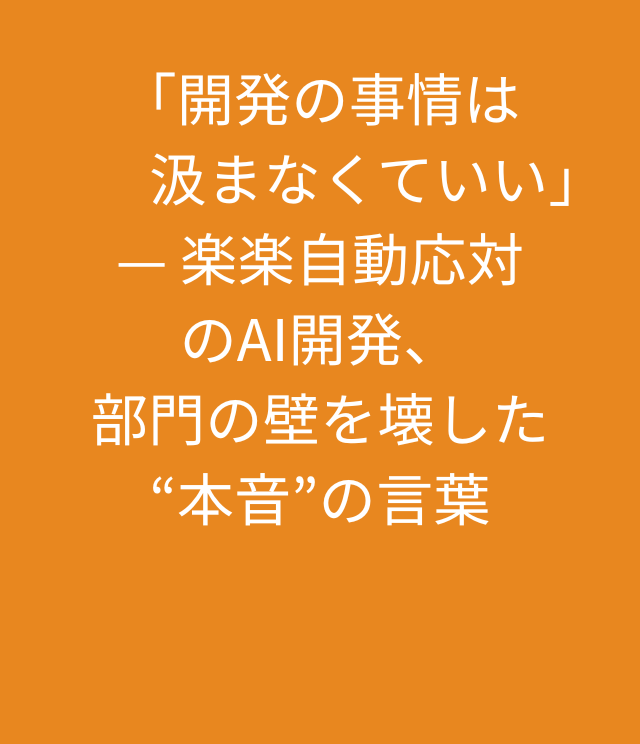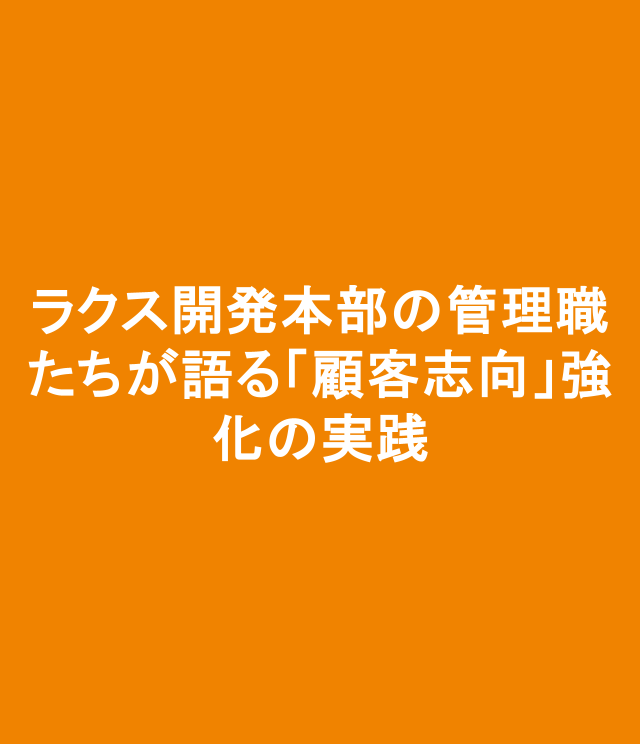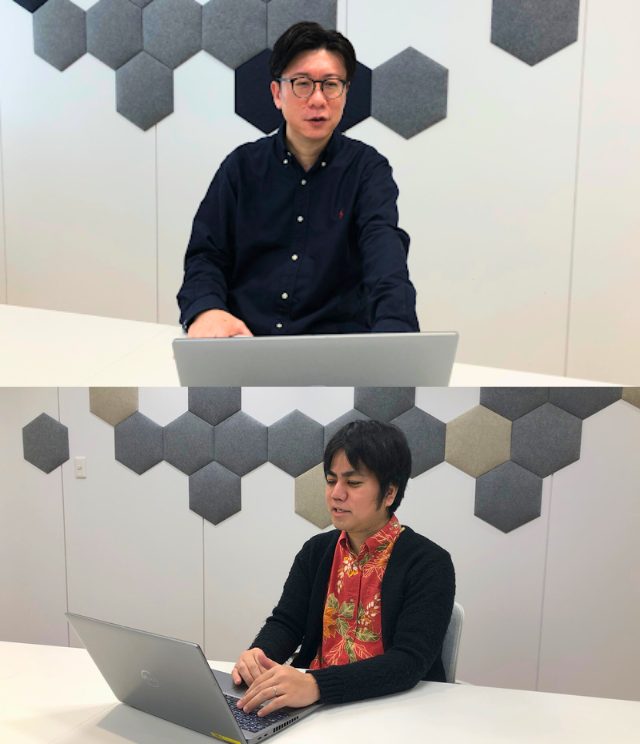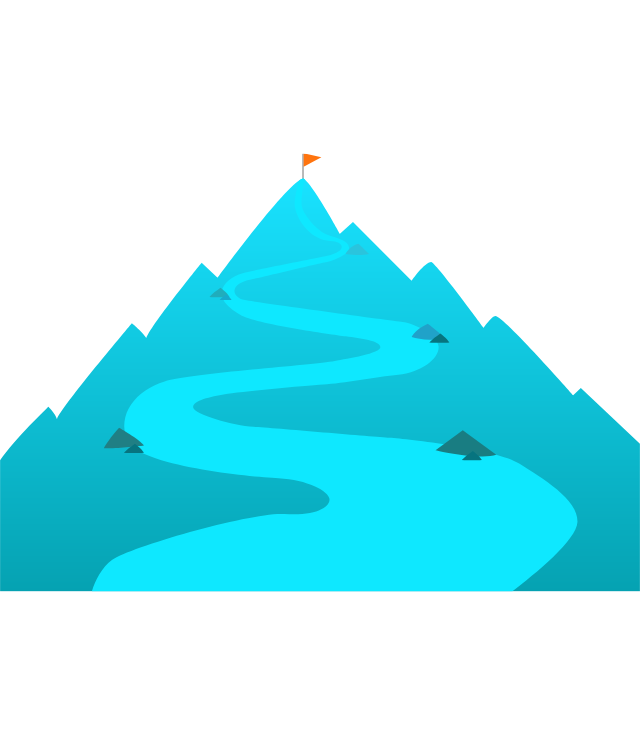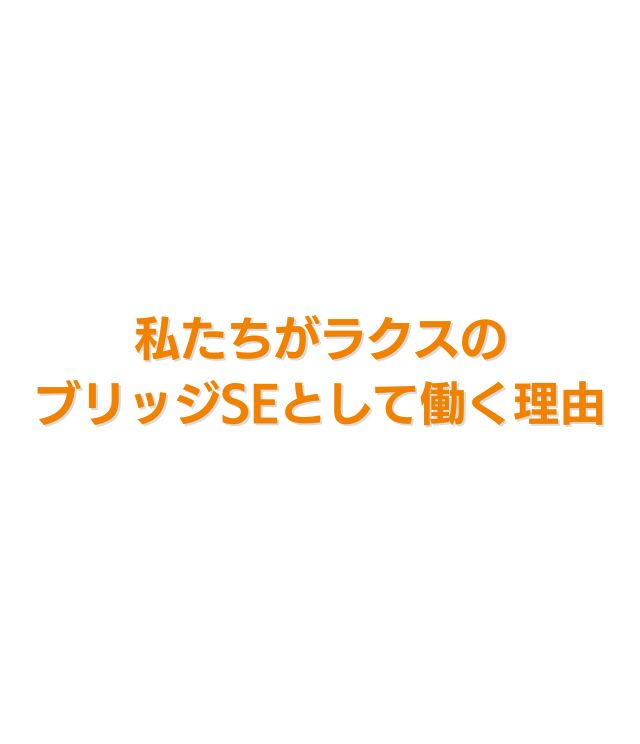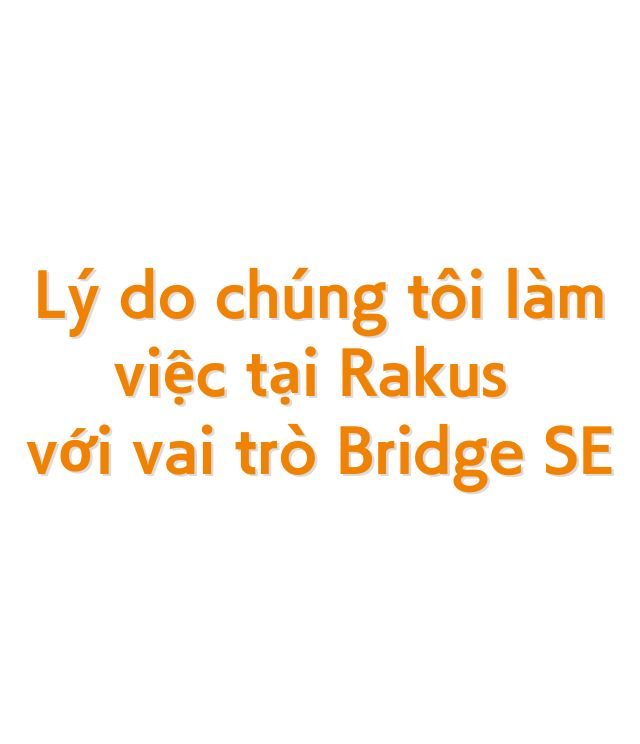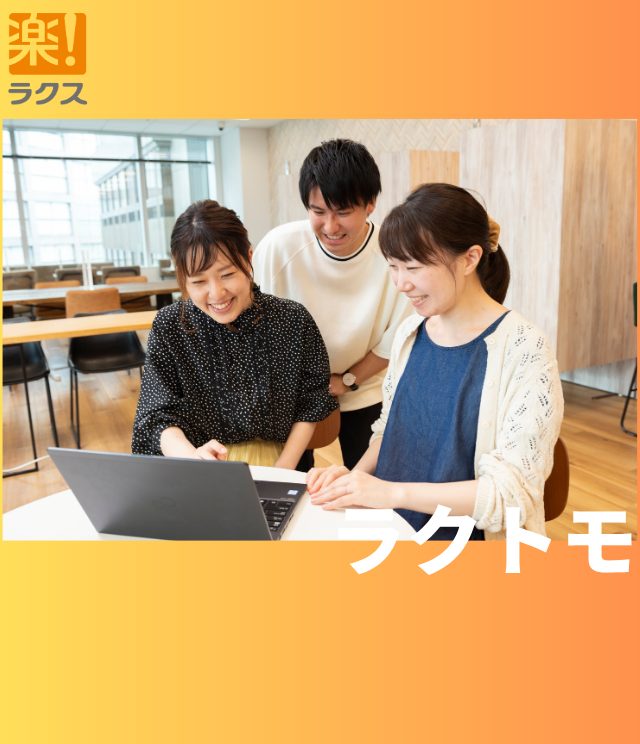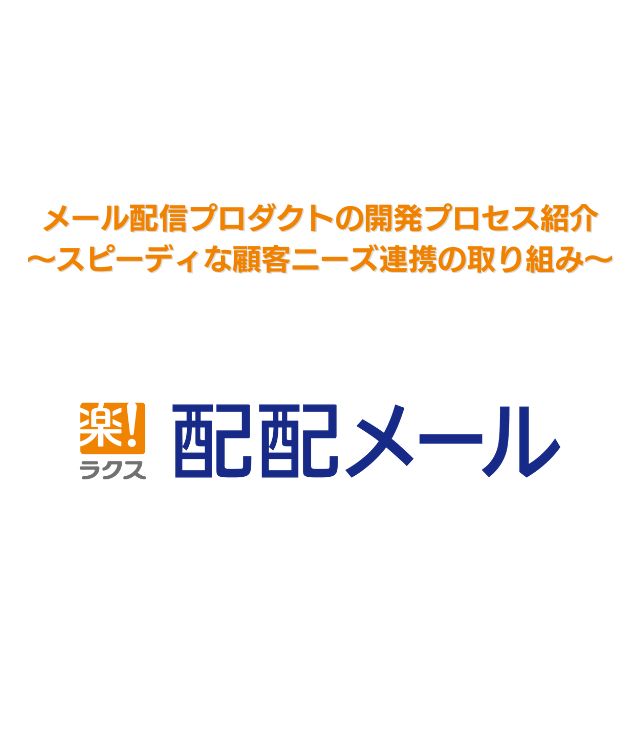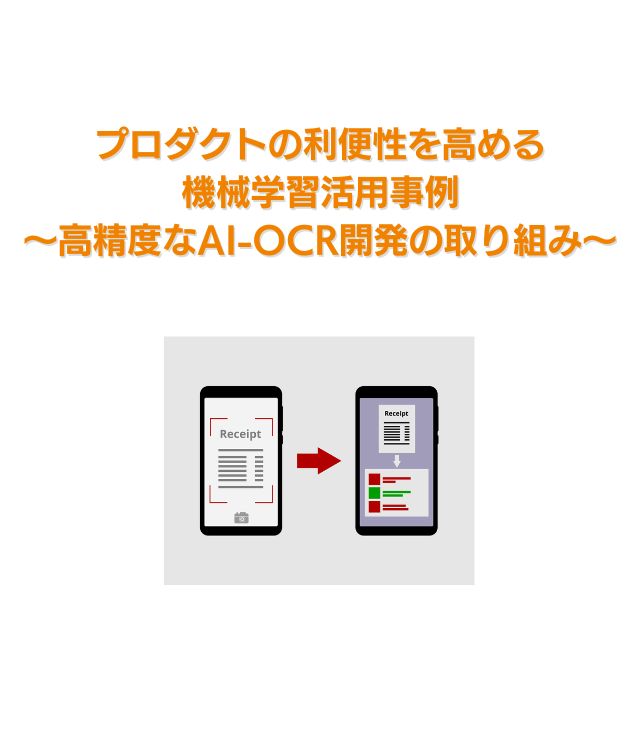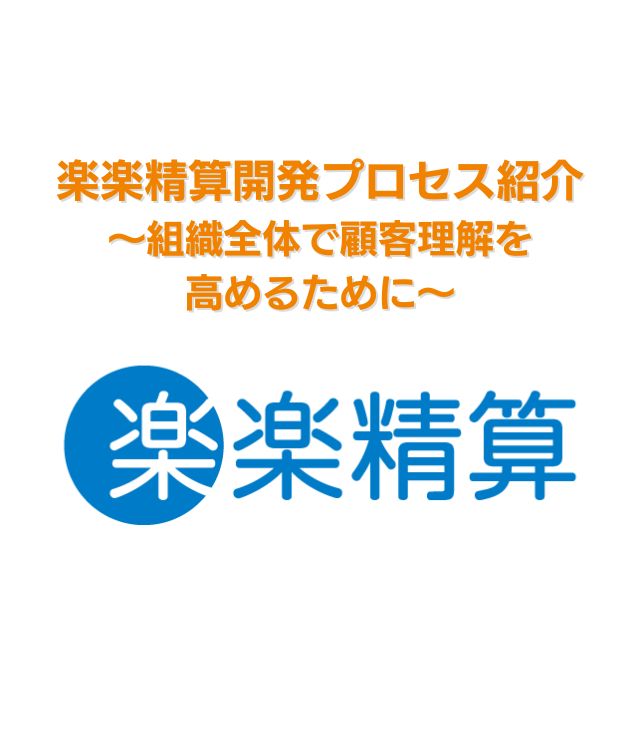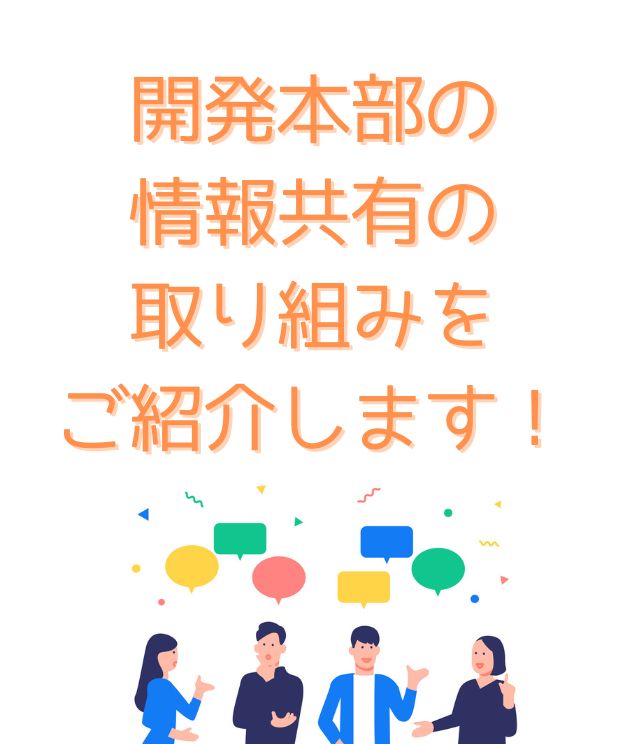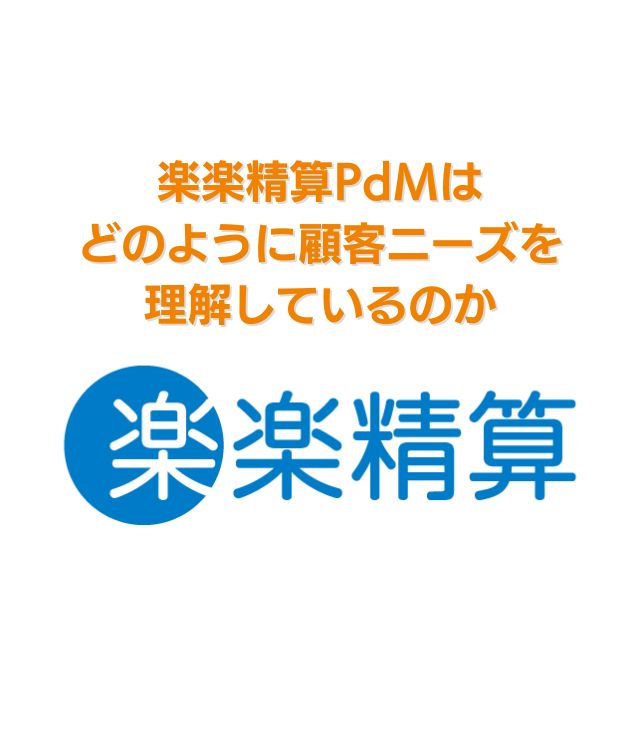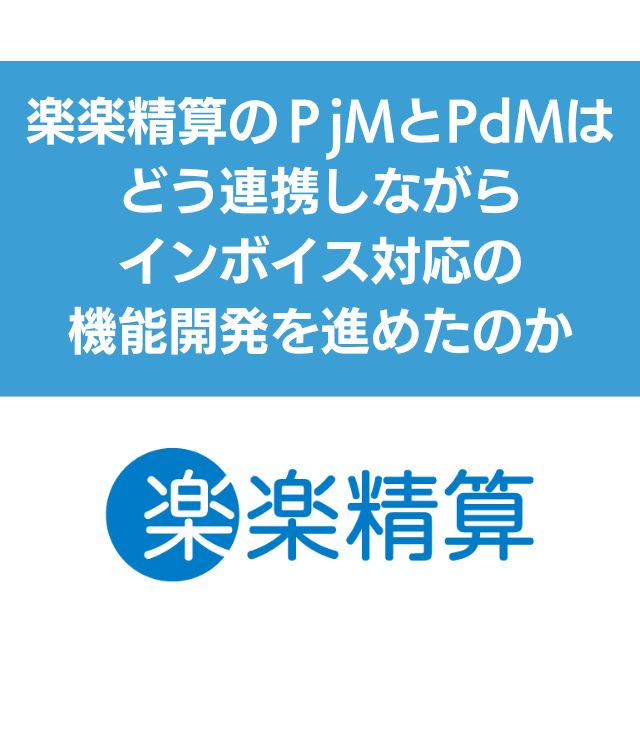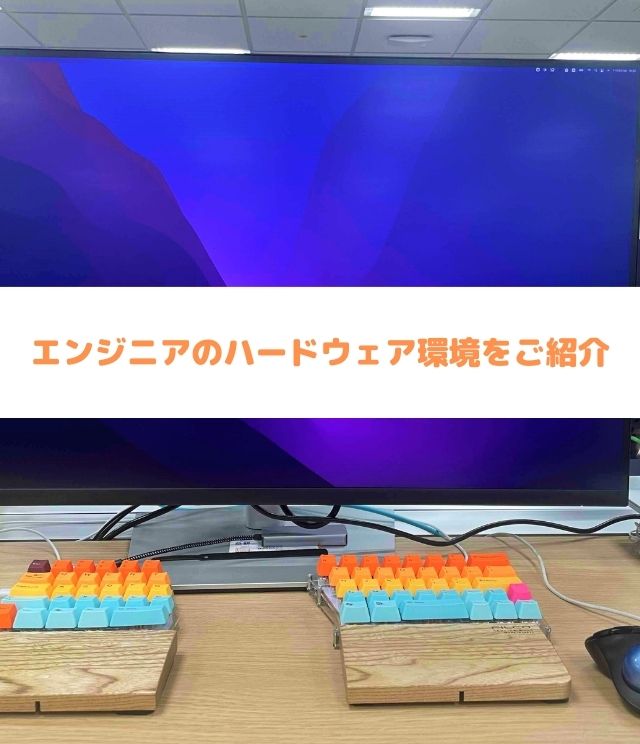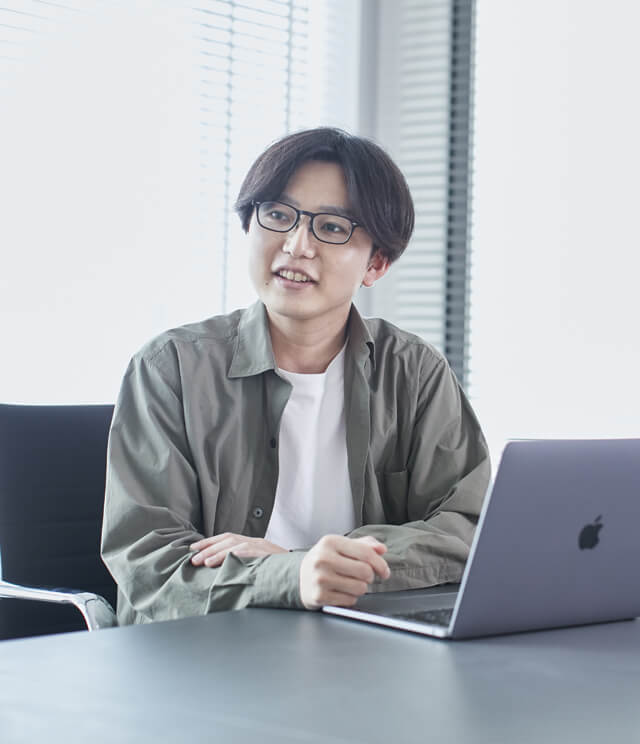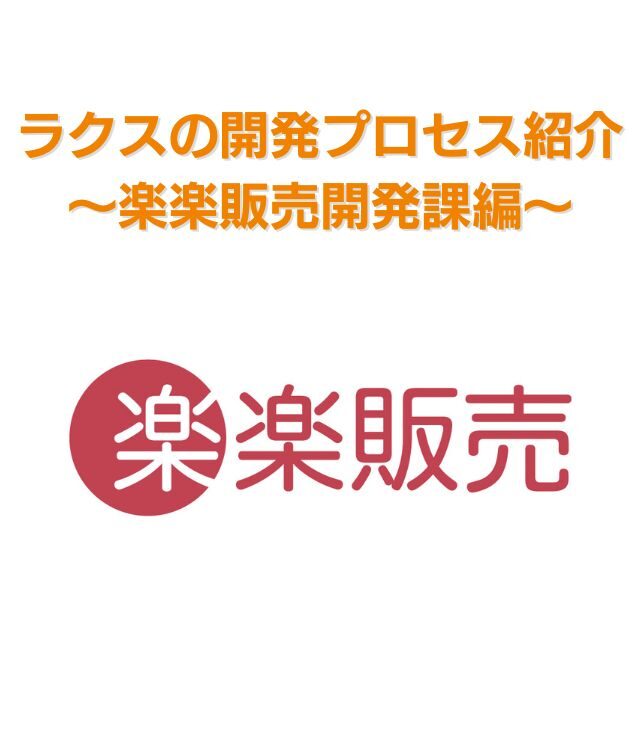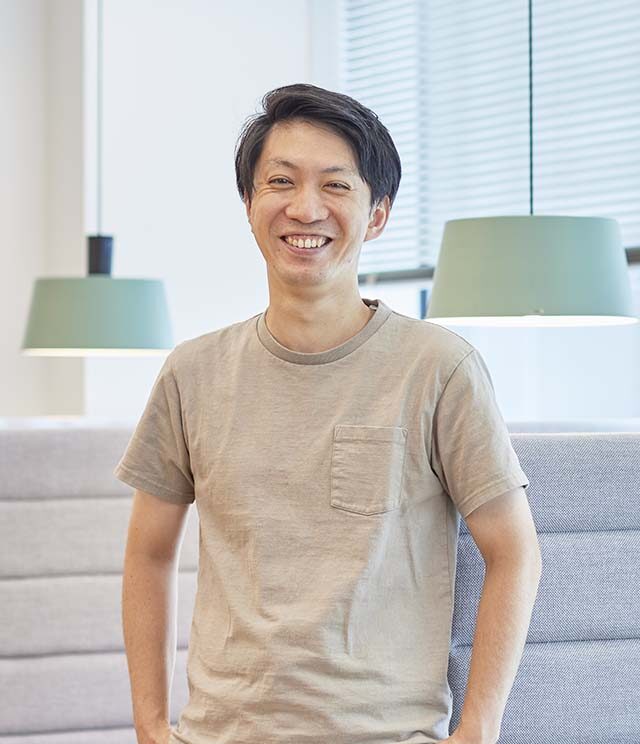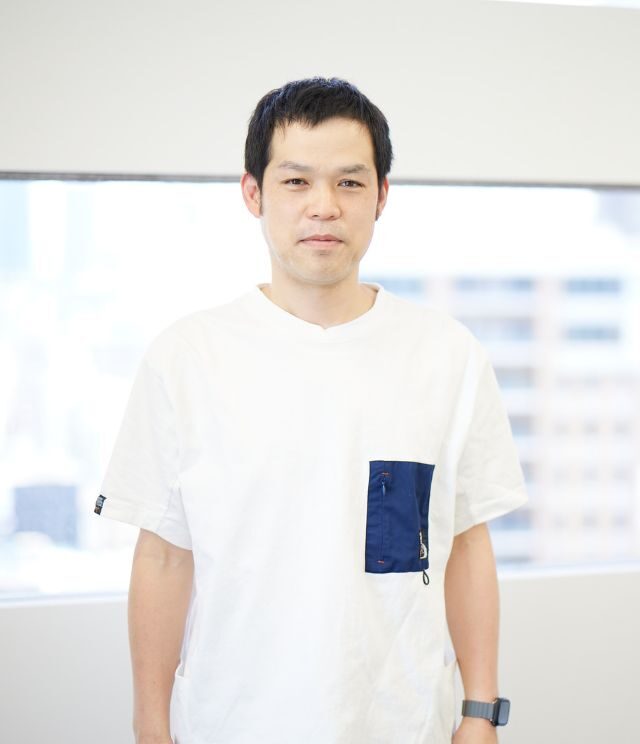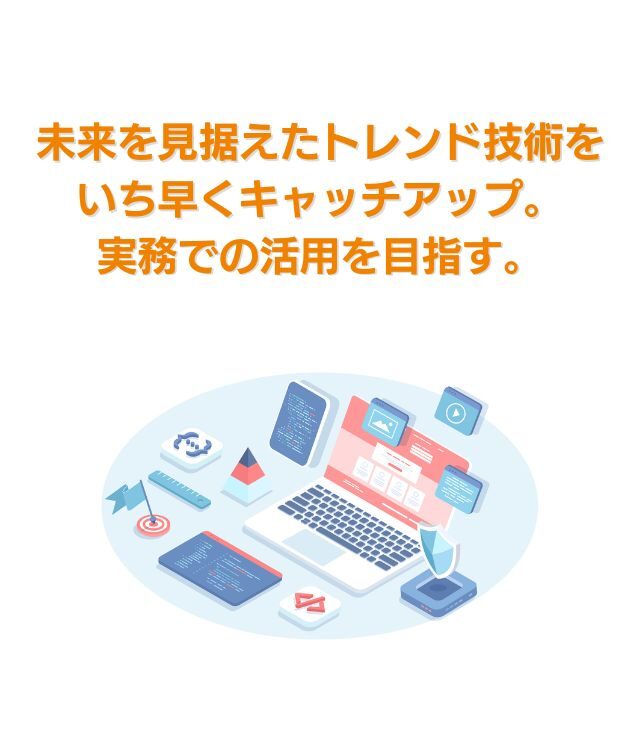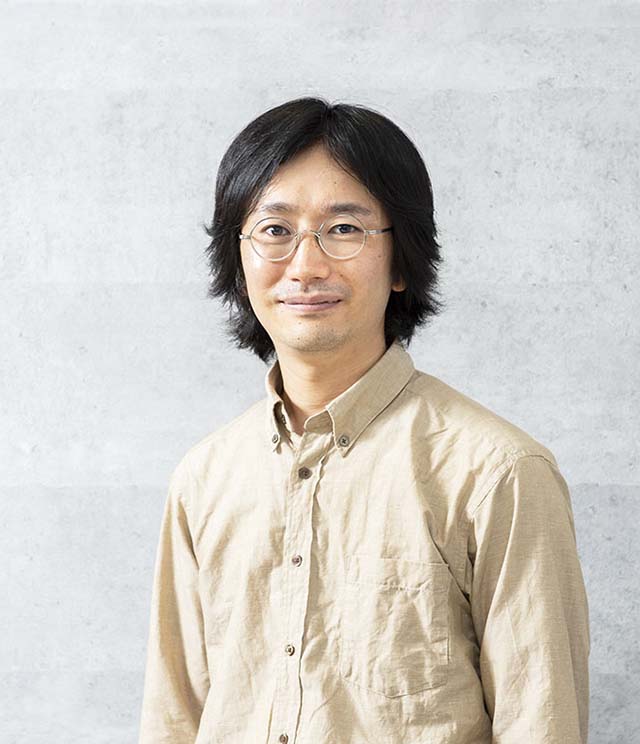PROFILE
伊藤 輝彦
医療業界向けのコンサルタントとして人事、採用、M&A、新規事業開発などを幅広く支援。名古屋、京都、札幌で営業責任者を務め、東京で人事責任者や新規事業立ち上げを経験。その後、2023年10月、新たなチャレンジの機会を求めてラクスに入社。札幌営業所のマネージャーを務め、北海道マーケットの開拓に尽力する。
競合が見当たらず、マーケットの約8割が白地
2022年10月に札幌営業所が開設されました。その背景から教えてください。
開設以前は、北海道の企業からの問い合わせに対しては東京からオンラインで対応していたと聞いています。あわせて、福岡で成果をあげた地銀連携の事例・ノウハウをもとに、北海道においても地元企業とのつながりが強い地銀との連携を探るべく、東京から出張で札幌を訪れる機会もあったそうです。
その際に地元の代理店を訪問するたびに、いつもより商談案件をいただけるようになったと。この経験から、北海道でキーになるのは「対面」だと、事業部として判断するに至ったと聞いています。
私が札幌営業所に加わったのは開設から1年後。営業活動を行っていると、確かに北海道の企業の皆さんは訪問すると快く時間を取ってくださいます。逆に、どうしてもオンラインでお話ししたいと言うと、「じゃあ次に来られるときでいいよ」と言われることも少なくありません。
こうしたビジネススタイルに順応するためにも、ラクスは北海道の約7割の企業が集まる札幌に拠点を構え、地元企業に寄り添い、Face to Faceによる課題解決を行うに至りました。
立ち上げ当時から今に至るまで、北海道のマーケットの状況はいかがですか?
立ち上げ時から地銀と連携し、行員の皆さんと地道に顧客を訪れては経理業務のデジタル化を提案しています。しかし、メインターゲットとなる企業のうちまだ約2割にしかアプローチできていない状況です。
それだけマーケットサイズが大きく、SaaS企業で他に北海道に拠点を構えている企業がほぼ見当たらないので、マーケットのほとんどが白地といえます。実際、クラウドサービスの活用はおろか、システムさえ未導入という企業が少なくなく、アプローチをよりいっそう加速させることが重要だと考えています。

発信力の高い企業・団体と連携し、セミナーによる啓蒙を強化
電子帳簿保存法(電帳法)改正やインボイス制度開始などによって、経理業務のデジタル化が一気に加速しましたが、北海道では違ったのでしょうか。
北海道においても問い合わせが増えたことは事実です。問い合わせのあったお客様先を訪問し、「楽楽精算」のデモンストレーションを行うと、「スマホで領収書を読み取れるの!? 思っていた以上に便利」と、デジタル化の利便性や必要性に改めて気づいていただき、導入に至るケースが多くあります。
しかし、そうした企業はごく一部といえます。北海道のマーケット全体を見渡すと、デジタル化の必要性があまり認識されておらず、紙と表計算ソフトを使った業務が当たり前のこととして行われています。
改善すべき課題が課題としてとらえられず、深く潜在化してしまっているということです。
まずは課題に気づいてもらうこと。そのためにどんな施策を行っていますか?
まずベースとなるのは、地道に企業訪問を重ねることです。地銀や代理店の方々と一緒にお客様を訪問しては、デジタル化の啓蒙・提案をコツコツと進めています。
くわえて、札幌を中心に企業のデジタルリテラシーを高め、デジタル化への意欲を醸成するために、セミナーの開催を積極的に行っています。
どのような内容のセミナーですか?
地銀との共催で年3~4回開催しているセミナーでは、DX推進や経理業務の効率化、郵便料金値上げへの対策などについて解説し、直近では札幌国税局の方にご登壇いただいて電帳法への対応についてお話ししていただきました。札幌国税局によるセミナーについては、札幌の企業へセミナー案内のDMを送ったところ、数十社から参加申し込みをいただき、セミナー後に商談へ至るきっかけになりました。
また、地銀との共催のほか、地元の新聞社や商工会議所等との連携も独自に進めており、地元で発信力の高い企業・団体と手を組むことで、啓蒙の裾野を広げ、デジタル化への機運を高めています。
そういう取り組みについて、他エリアの事例も参考にしているのですか?
はい、地銀連携の施策は全国各地のエリアで行われており、エリアを横断してその事例・ノウハウを共有する場を設けています。実は私がその場のオーナー役を務めています。
現在、全国各地の地銀担当が約50名参加し、地元企業向けのセミナー・展示会の好事例や、地銀から商談案件をいただくためのポイントなど、さまざまな観点からノウハウを披露しあい、各エリアで施策の企画やマーケティング、受注率の向上に役立てています。

一人ひとりの存在が大きく、視座を高められるフィールド
いろいろと施策を試みている段階なのですね。
そうです。他エリアの事例・ノウハウを参考にしながら、どんな施策が北海道のマーケットにフィットするのか、トライしては検証し、次に生かすというプロセスを重ねています。
明確な勝ちパターンを見出だしていない状況なので、「新しいことをどんどんやってみよう」というスタンスです。やってみないことには成功も失敗もなく、何も始まりませんから。
メンバーからも「こうしたい」という意見が上がってきますか?
はい、かなり活発にあがってきますよ。例えば「楽楽明細」の営業メンバーは、代理店各社のメーリングリストを作成し、定期的に商材情報や営業ノウハウなどを発信してフォローするという施策を提案。即実践に移してもらったところ、代理店からの問い合わせが増え、商談依頼が届くようになりました。
自らの考えが施策に反映される魅力は、立ち上げ期ならではのことですね。
まだまだコンパクトな組織ということもあって、一人ひとりが役割を限定せず、自ら裁量権をもって代理店との連携や提案・受注、顧客フォローを行っています。札幌営業所全体にかかる施策やしくみづくりについても、自由にアイデアを出し、具現化に動いています。
既存のしくみや仕事にとらわれるのではなく、より視野を広げ、視座を高められる環境ですから、自分自身の成長スピードも格段に高めることができるはずです。

組織拡大とクロスセルが本格化し、チャンスが拡大
今後の展望についてお聞かせください。
札幌営業所は定員4名のレンタルオフィスからスタートし、2024年10月には組織拡大を見据えてオフィスの拡張移転を行いました。そして、人員の増員によって、札幌を中心に函館、帯広、旭川等へ訪問エリアを拡大させ、商材についても「楽楽精算」に続いて「楽楽明細」へ本格的に広げています。
今後については他商材営業メンバーも札幌営業所に加わり、マルチプロダクトの提案をより一層力を入れて挑みたいと考えています。組織も数十名体制に拡大を予定しているので、オフィスのさらなる拡張も計画しています。
組織の拡大・強化によって、広大なマーケットの開拓スピードを高めるとともに、各商材のメンバー・チーム間で丁寧にトスアップを行い、クロスセルを組織的に推進していく構えです。そして、お客様1社1社にすべての商材を導入し、北海道全域にデジタル化の恩恵を広げていきたいと思っています。
キャリアのチャンスについてはいかがでしょうか?
チャンスは広がるばかりです。組織拡大に向けて、リーダー・マネージャーのポジションを担えるメンバーの育成が急務だと思っていますし、実際、メンバーたちは一人ひとりがリーダーシップをもって仕事に取り組んでくれていますので、早期にキャリアアップを叶えてくれるでしょう。
もちろん、これから加わっていただく新しい仲間にも、チャンスは平等です。
どんな人にその仲間に加わってほしいですか?
「こうしたい」「こんなことをやってみたい」と、積極的に声をあげてくれる人にぜひ来てほしいと思っています。どんなことも自由にやれるというわけではありませんが、筋が通り、可能性を感じるアイデアであれば、積極的にGOを出し、任せていくのが私のスタイルです。もちろん助言やフォローを惜しみません。
小さな施策でも、PDCAを素早く回して成果を出し、再現性を高めて営業所全体に展開すれば、より大きな成果へと繋げることができます。その過程で新たなスキルや視点が身につき、自身の成長へと繋がるでしょう。
※所属・役職はインタビュー時点(2025年2月)のものです。