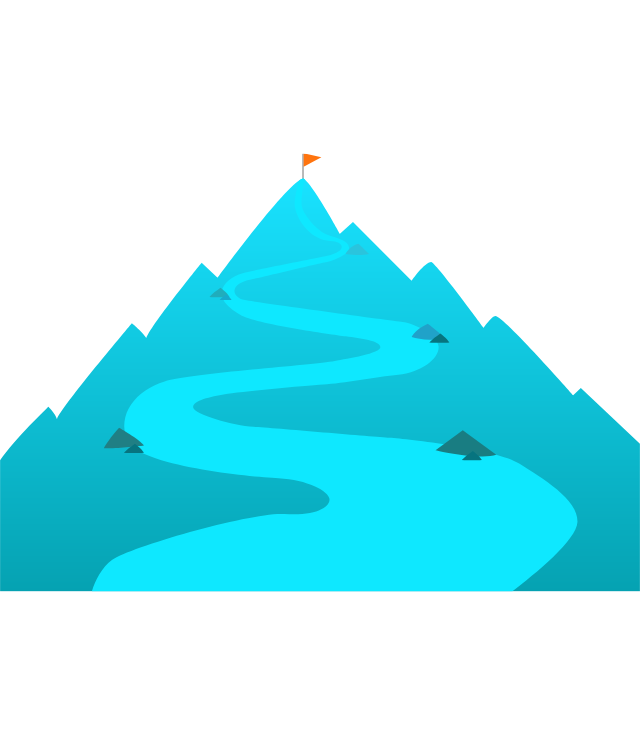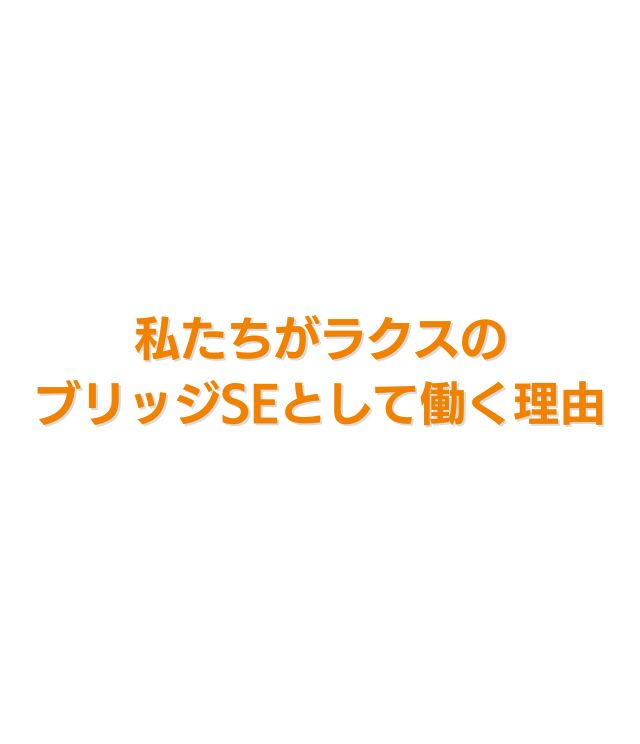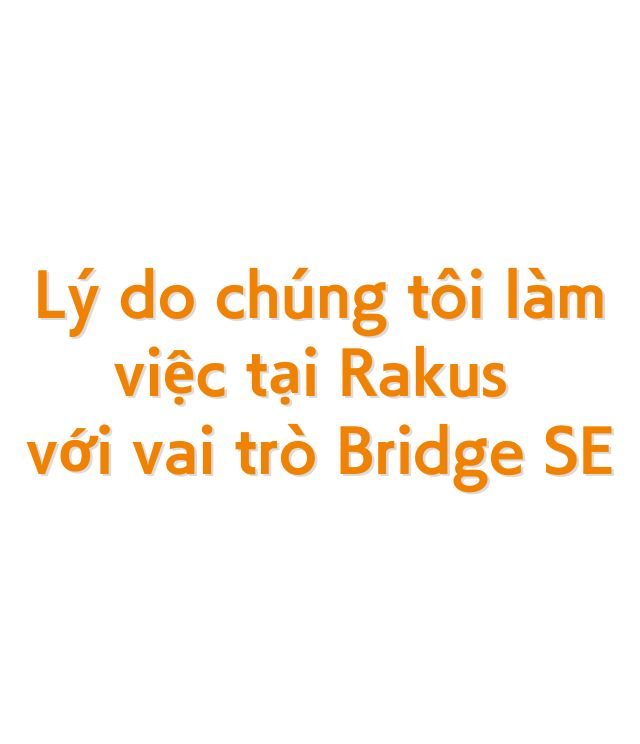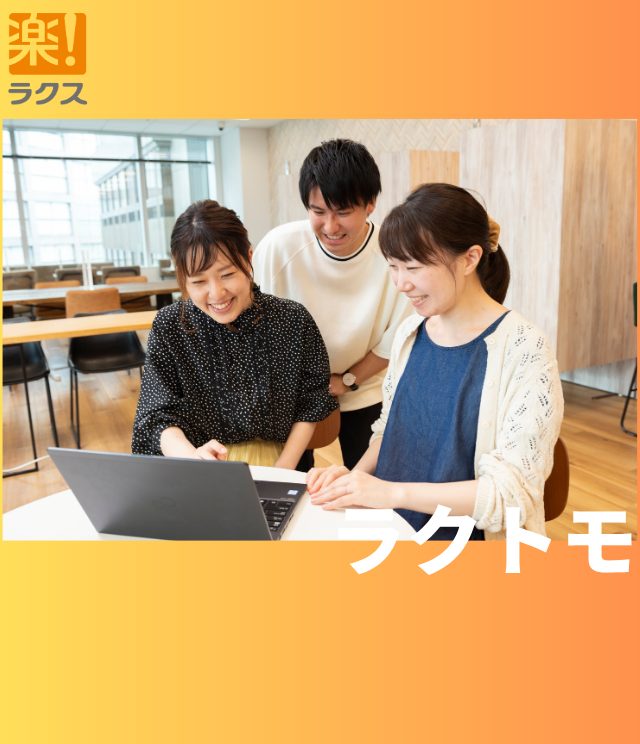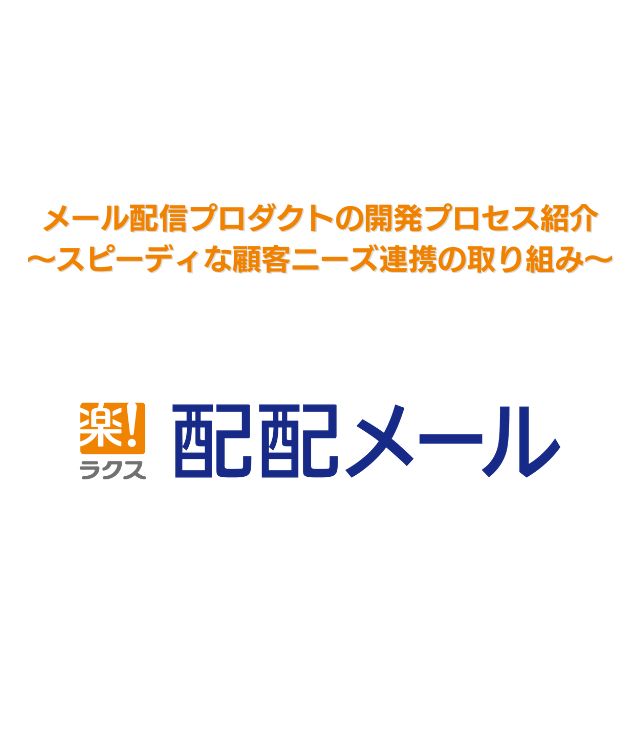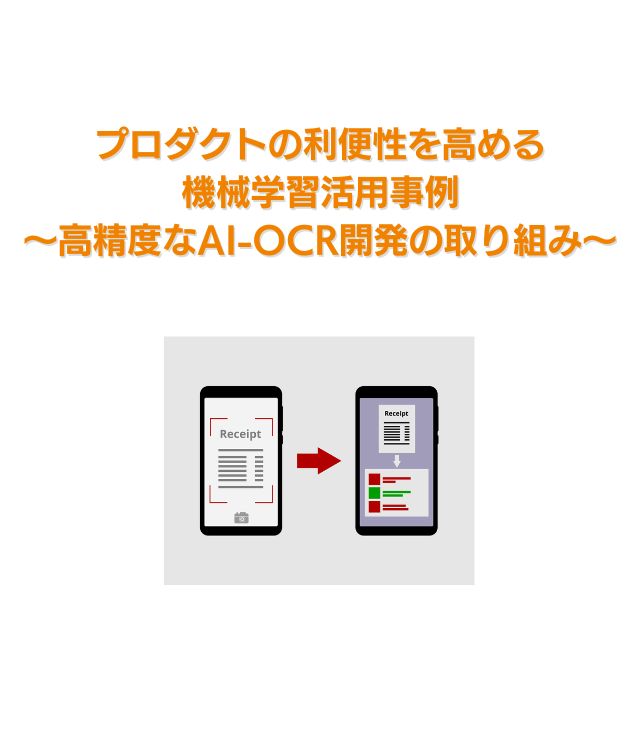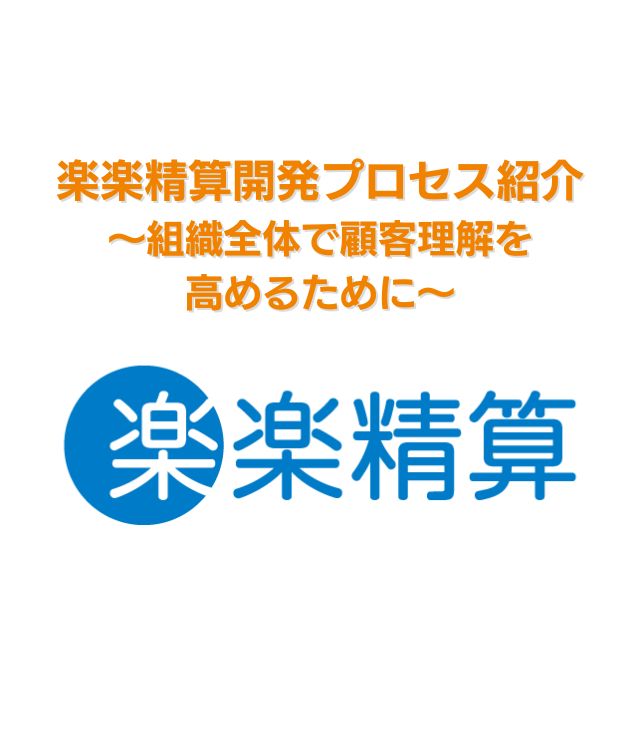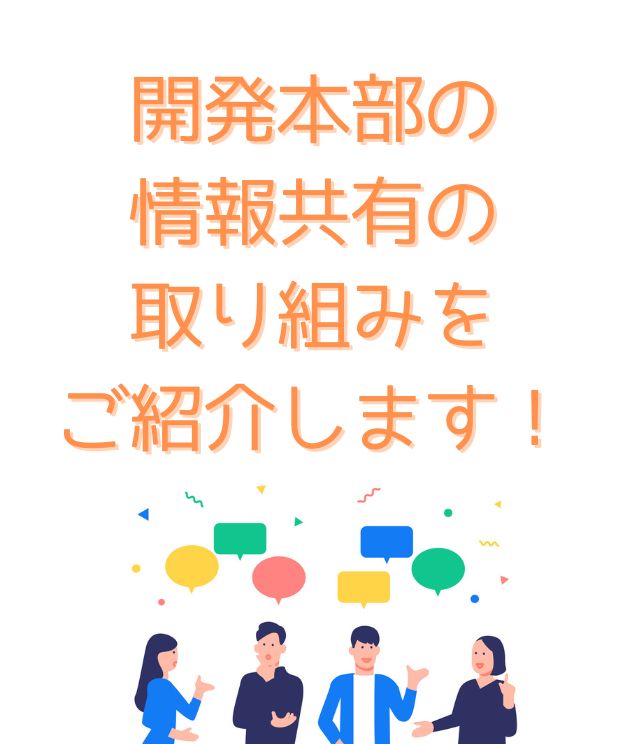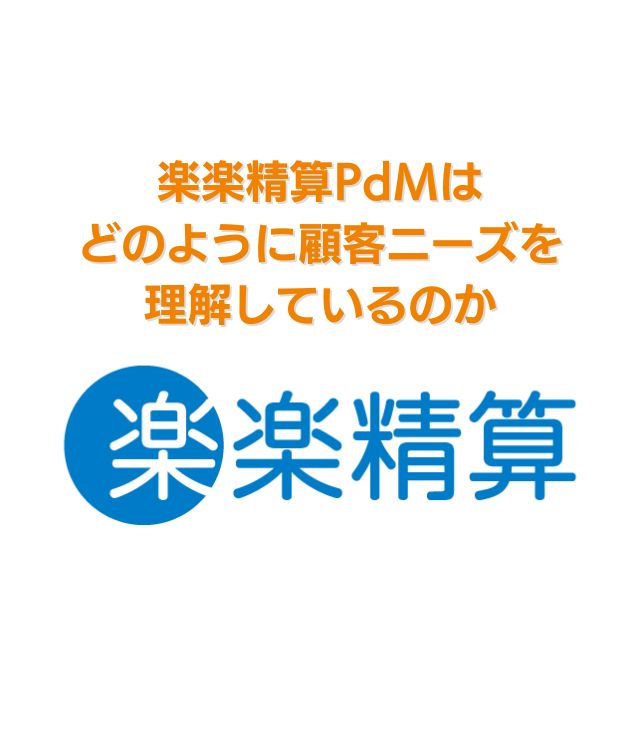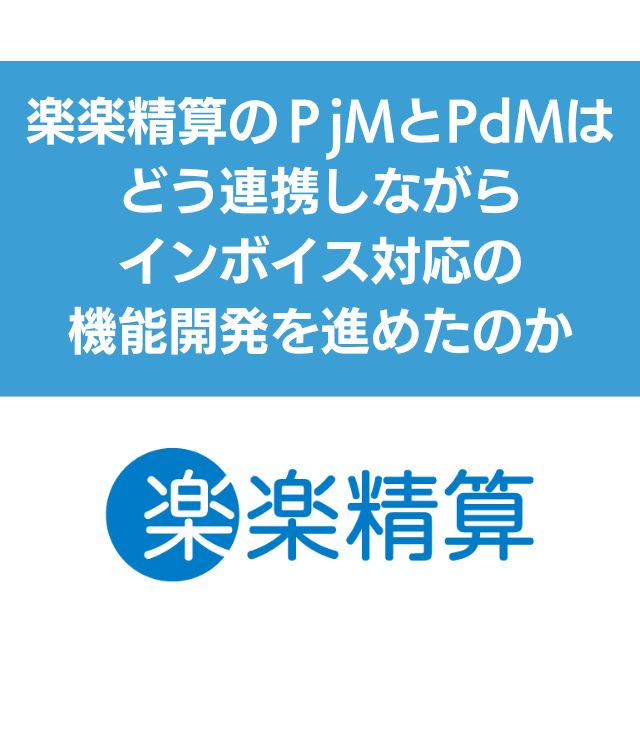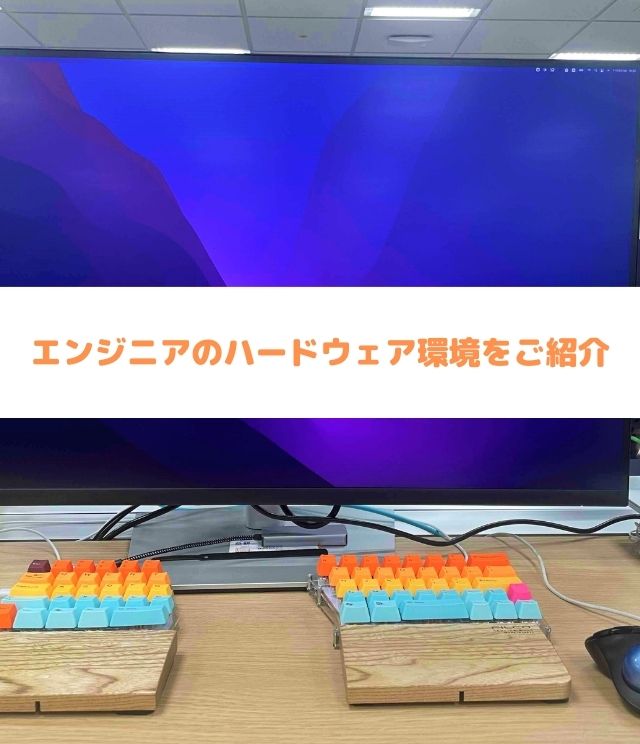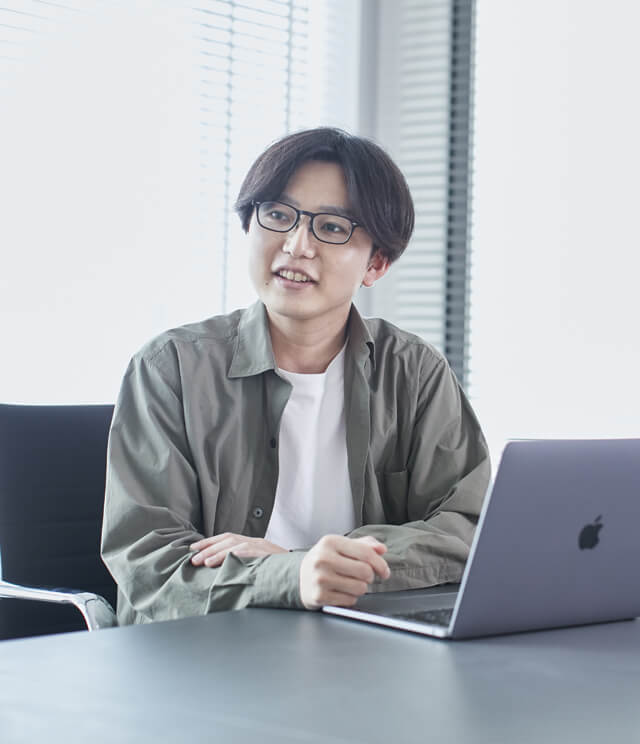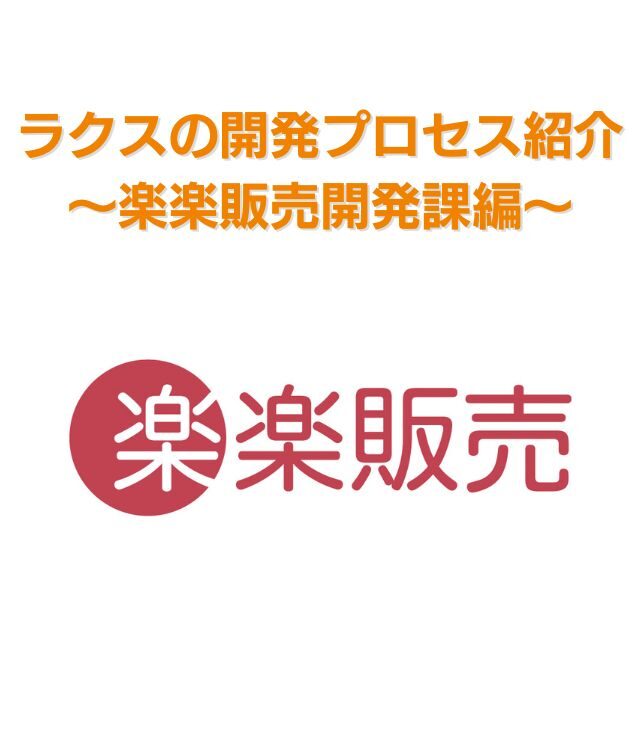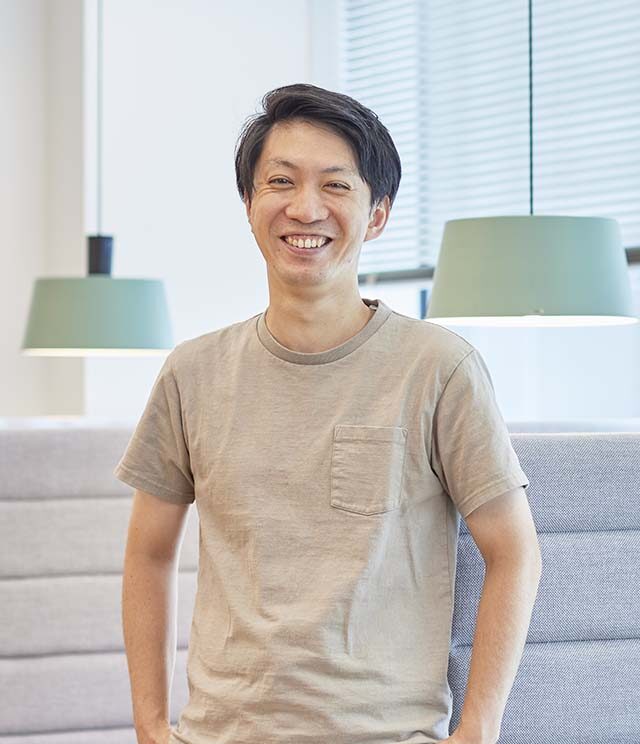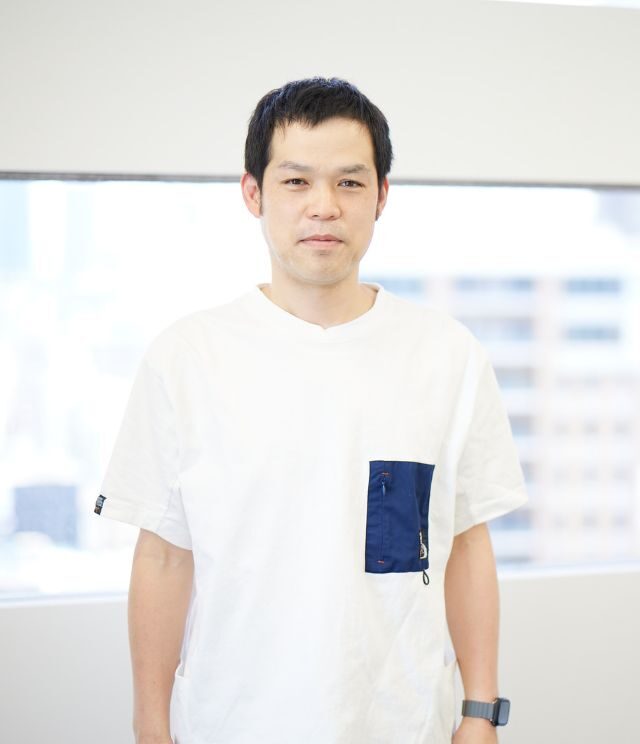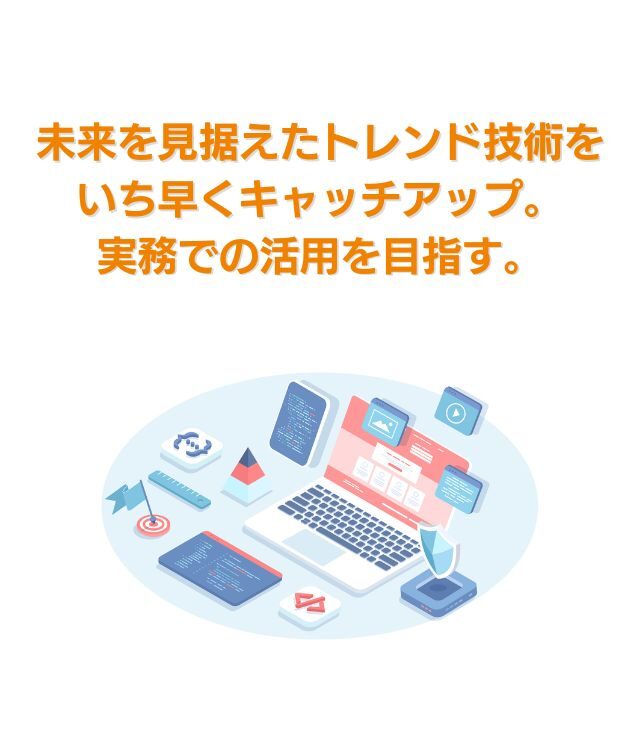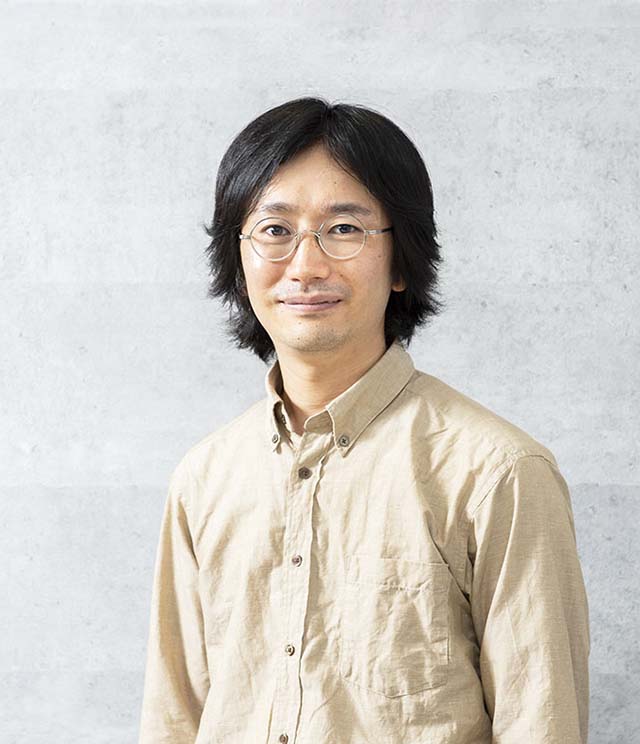PROFILE
髙野 俊亮
楽楽クラウド事業本部 楽楽クラウド事業本部 楽楽請求事業統括課 西日本カスタマーサクセス1課
大学卒業後、コールセンター向けBPO企業に就職し、センター運営や営業、事業管理などを担当する。35歳を前に今後のキャリアについて考え、第一子誕生もきっかけとなって転職を決意。2022年1月、ラクスに入社。「楽楽精算」のカスタマーサクセスを経て、2024年10月にリリースした「楽楽請求」のカスタマーサクセスを立ち上げからけん引する。
導入して終わりではなく、顧客の生産性向上をゴールに
まず「楽楽請求」の特徴を教えてください。
「楽楽請求」は、請求書の受領・管理に特化したクラウド型システムです。紙の請求書はまとめてスキャン、電子データは自動アップロードによって一元管理し、AI-OCR機能によって請求書の日付・金額・支払先などの情報を自動で読み取ります。そして、仕訳・振込データを会計ソフトに応じて作成・出力し、請求書の受領漏れや入力等の手間とミスの防止、データ管理の効率化を実現しています。
これは「楽楽精算」の一機能が派生して生まれたサービスであり、リリースしたのは2024年10月。請求書受領システム市場では後発ではありますが、「お客様にとって本当に使いやすいのは何か」を追求し、お客様の声をもとに日々進化を続けることで、導入実績を伸ばしています。
カスタマーサクセス(CS)は、どのようなミッションを担っていますか?
私たちCSの役割は、単に操作方法を案内することではありません。お客様の業務に深く入り込み、請求書受領にまつわる「面倒くさい」「手間がかかる」といった根本的な課題を解消することが使命です。
「楽楽請求」の導入はゴールではなくスタート地点。お客様が「請求業務の煩雑さから解放され、より付加価値の高い仕事に時間を使える」状態を共に描き、その実現に伴走していきます。
具体的にはどんな課題に対応しているのでしょうか。
例えば導入前は、多くのお客様が受け取った請求書の内容を一つずつ確認・仕訳し、会計ソフトに入力されています。丁寧な作業である一方で、どうしても多くの時間や工数が必要となり、他の業務との両立にご苦労されるケースも少なくありません。
また、企業によっては受領した請求書を複数の管理者が確認し、承認を得るフローが必要になります。こうしたプロセスを紙や表計算ソフトで運用されている場合、関係者間での確認や進捗管理に思った以上の負担がかかってしまうこともあります。
「楽楽請求」をご利用いただくことで、AI-OCRが読み取った情報を元に仕訳を生成し、会計ソフトとのデータ連携までスムーズに完了します。これにより入力作業にかかる時間を大幅に削減できるほか、承認フローもシステム上で回せるため、これまで複雑だった管理も効率的に進められるようになります。
請求書受領と一口に言っても、さまざまな業務が絡み合っているのですね。
どんな工程に手間と時間がかかっているのか、どういう状態になるのがベストなのかは、お客様によってさまざまです。そのため、私たちCSは、お客様との初期のミーティングではお客様の業務フローの整理から始め、「業務全体の生産性を向上させる」という共通のゴールを設定し、安心して運用できるように伴走しています。

導入から定着まで、改善を積み重ね、お客様に寄り添う伴走体制
ミッションを果たすために、どのような進め方を行っていますか?
お客様の成功支援に向けて、運用開始と運用定着それぞれのアプローチを定義しています。
運用開始時においては、Webミーティングやメール、電話などのハイタッチによる支援の手順をまとめています。運用定着に向けては、お客様の稼働状況をログデータのモニタリングやヒアリング、アンケートなどを通して把握し、運用後に発生する課題の解決に継続的に寄り添うフローを共有しています。
こうした定義は、どのようにしてつくられたのですか?
CSの立ち上げメンバーや戦略部門のメンバーと一緒に、5~6名で「楽楽請求をご利用されるお客様の理想の状態とは何か」という観点から検討を始めました。
そこで掲げた成功状態は、「お客様が安心して運用し、日々の業務をよりスムーズに進められるようになること。その結果、サービスへの満足度が高まり、将来的には他のクラウドサービスでも効率化を広げていただける状態」 です。
この理想像をもとにカスタマージャーニーマップを描き、各フェーズで必要となる支援を整理しました。支援を実際に行いながら、PDCAを回して改善を重ねています。
例えばどんなブラッシュアップ?
運用開始時の支援においては、2カ月間の無償サポート期間を設け、お客様の運用開始を支援してきました。その過程で、「お客様がよりスムーズに運用を始められ、早期に効果を実感していただくにはどうすればいいか」という視点で最適解を考え続け、検討を繰り返しました。
運用開始の支援を手厚くすることはもちろん重要です。しかし、お客様には運用してみて気づく困りごとや課題があることも事実。
そこで、現在は運用開始の支援を1カ月間に短縮し、後半の1カ月間を運用後に露呈した実際の運用で見えてくる課題の解消にあてるというフローに進化させました。そうすることで、お客様にとって2カ月間の使い方がより有効になり、早期の課題解決と運用定着に結びつくと考え、チームで鋭意取り組んでいるところです。
導入支援を1カ月間短縮するとなると、メンバーに負荷がかかったのでは?
新たなフローをキャッチアップする必要があり、確かに簡単ではありませんでした。
ただ、CSチームではナレッジ共有ツールを活用し、メンバー全員が支援の中で得た知識やノウハウをすぐに共有できる仕組みを整えています。そのため、わからないことが出てきても「一人で抱え込む」ことはなく、ツールを見れば解決のヒントが得られる環境があります。さらに、先輩メンバーへの相談もしやすく、チーム全体で新しいフローを学び合いながらキャッチアップできる体制です。

立ち上げ期だからこそ、仕組みづくりを行いながら自己成長を実感できる
新しい製品だからこそ、今加わればいろんなチャレンジができそうですね。
そのとおりです。PDCAを早いスパンで回しながら、最適な仕組みを構築している段階ですから、これからジョインしていただく方も早期に自分の意見をサービス・仕組みづくりに反映するチャンスがあります。
メンバーが仕組みづくりを主導した事例もありますか?
はい、あります。
例えば、新しいオプション機能「受取代行オプション」のフローの構築です。
これは、紙やメールにてさまざまな形式で届く請求書の受領~アップロードを代行する機能で、2025年10月からオプションとして利用可能としています。この機能のお客様へのご案内やオペレーションのフローは、同年4月に当チームに加わったばかりのメンバーが中心となってつくり上げたものです。
仕組みをつくるのは簡単ではないこと。だからこそやりがいも大きそうです。
はい。今の「楽楽請求」には、既存のやり方に沿って業務を進めるだけではなく、仕組みそのものを変えたり、新しい流れを生み出すチャンスがあります。立ち上げ期だからこそ、変化もスピードも大きいんです。
そうした環境を、自分の成長の機会ととらえられる方なら、早い段階からやりがいを実感できると思います。実際、チームにはそうした「変化を楽しむ」姿勢を持った人が集まっています。
そうしたチャレンジの課程で、どんなスキルを磨くことができますか?
一つは、汎用性の高い「折衝・交渉力」です。
新しい機能やサービスをつくったり改善したりする際には、開発やマーケティング、法務など、さまざまな部署と連携する必要があります。
例えば、ユーザビリティの向上をめざすうえでは、プロダクト戦略部門との連携が欠かせません。むしろ恒常的にお客様に寄り添い、お客様の困りごとに触れているCSの意見を求められる場面が多くあります。新しいオプションを実装する際には、事業管理部門と一緒に機能設計やルールを検討したり、利用申込書の仕様については法務部門に確認したりします。CSはお客様の課題を一番近くで理解している存在なので、「なぜこの機能が必要なのか」と背景や目的をわかりやすく伝え、社内を巻き込んで改善を進めていきます。こうした経験を積むことで、自然と調整力やコミュニケーション力が磨かれていきます。
さらに、「楽楽請求」では前例のない課題に挑む機会も多くあります。その都度、KPIを設定し、達成までの道筋を想像し、仮説を立てて検証していく必要があります。こうした経験を通じて、想像力や論理的に考える力が日々の業務を通じて養われていきます。

メンバーそれぞれの活躍チャンスを広げたい
そうしたチームを率いる髙野さんが、マネジメントで意識していることは?
メンバー一人ひとりが「どんな挑戦をしてみたいのか」という本音を引き出し、その思いに沿った役割やポジションを任せることが、マネージャーである私の大事な役割だと思っています。
実際に、あるメンバーは「仕組みづくりに挑戦したい」という意欲を持っており、オプションオンボーディングの構築を担当しました。その成果を事業本部長に報告したところ、すぐに「他プロダクトのオプション利用促進に向けて知見を貸してほしい」と依頼が届いたんです。本人からはとても喜んでいる様子が伝わってきて、その姿を見て私自身もうれしくなりました。
このように、メンバーの挑戦が社内から認められ、次の活躍につながるシーンは少なくありません。だからこそ、これから加わってくれる方にも、自分のやりたいことを積極的に発信し、変化を楽しみながら成長していってほしいと思います。
※所属・役職はインタビュー時点(2025年8月)のものです。