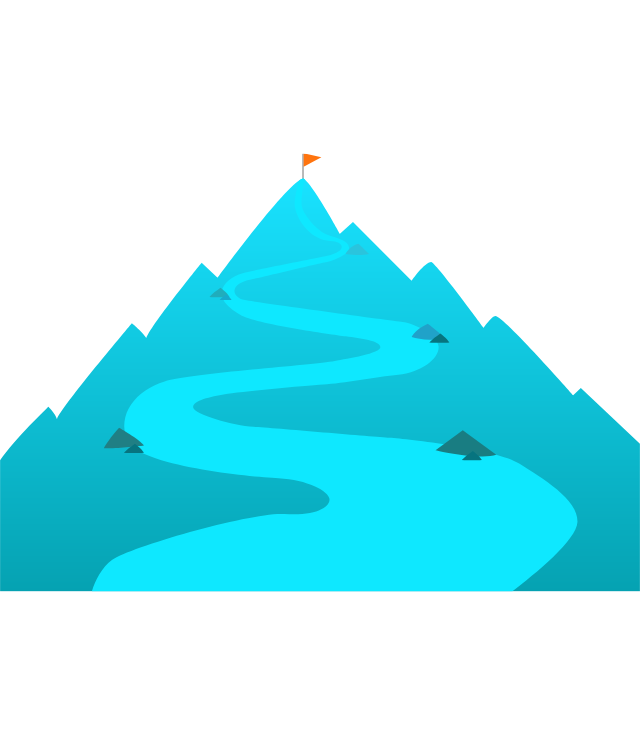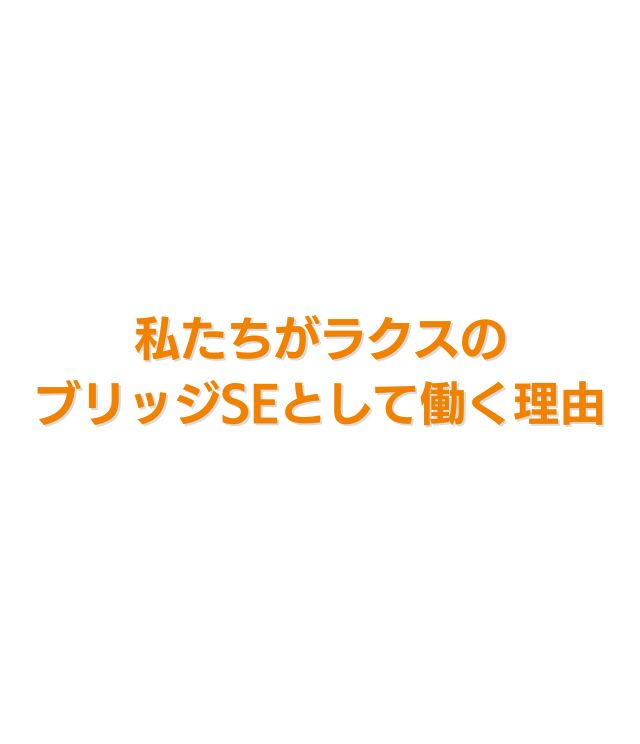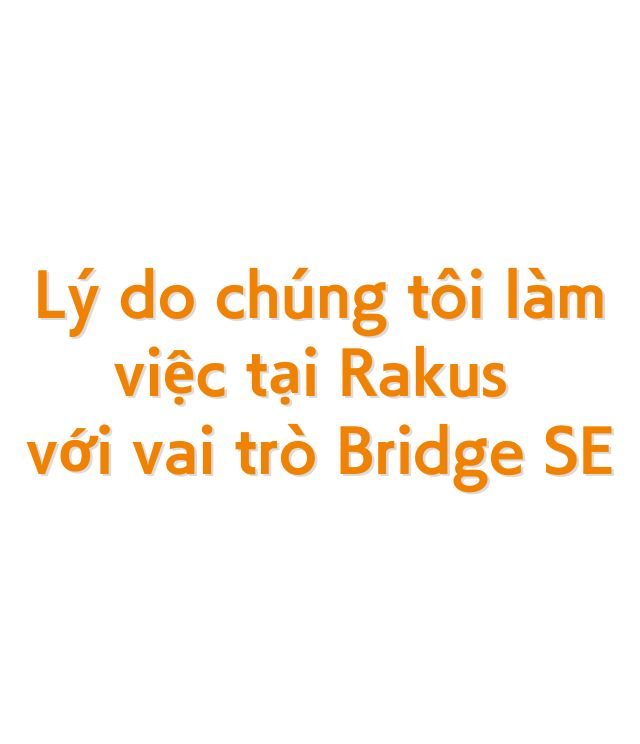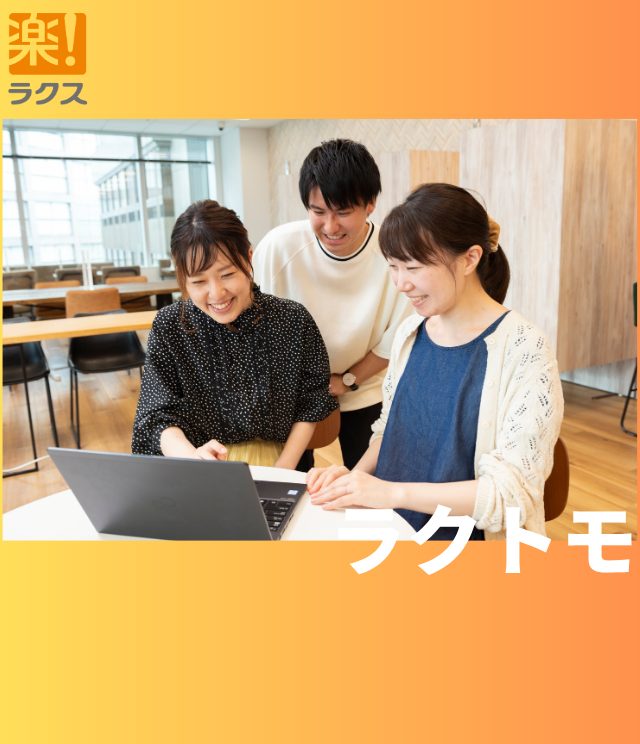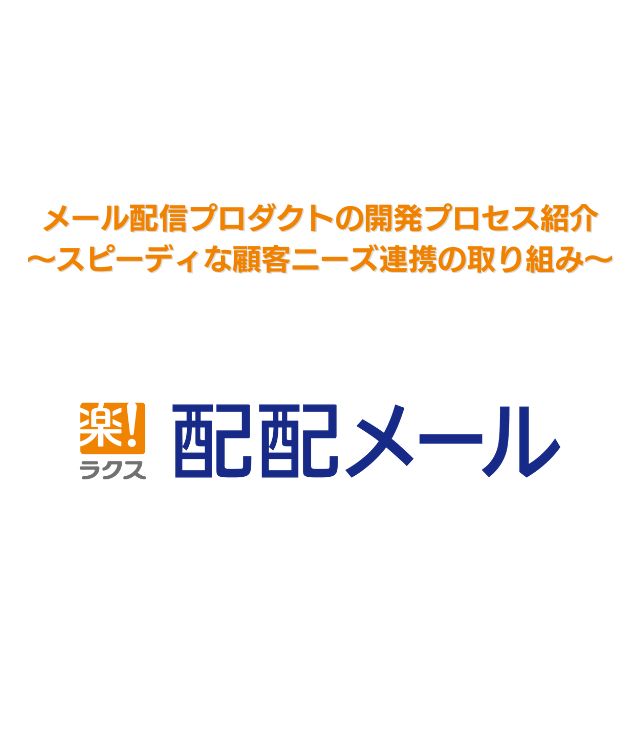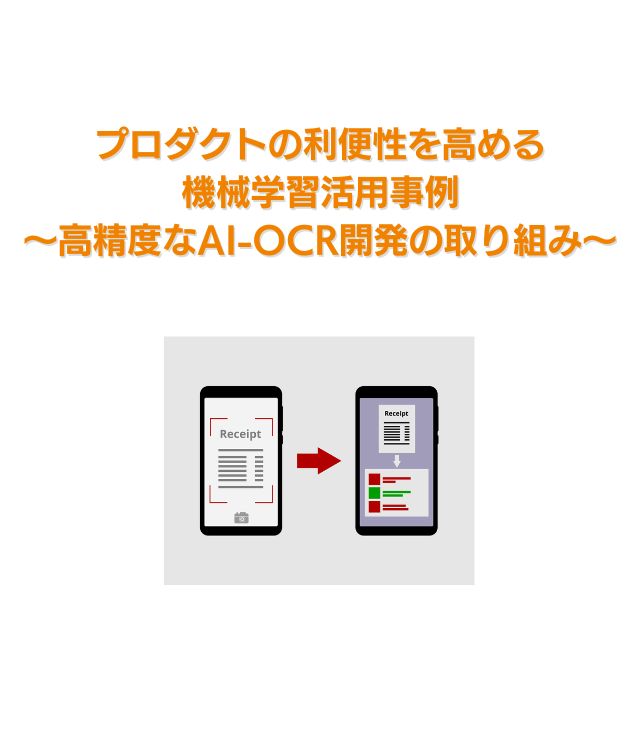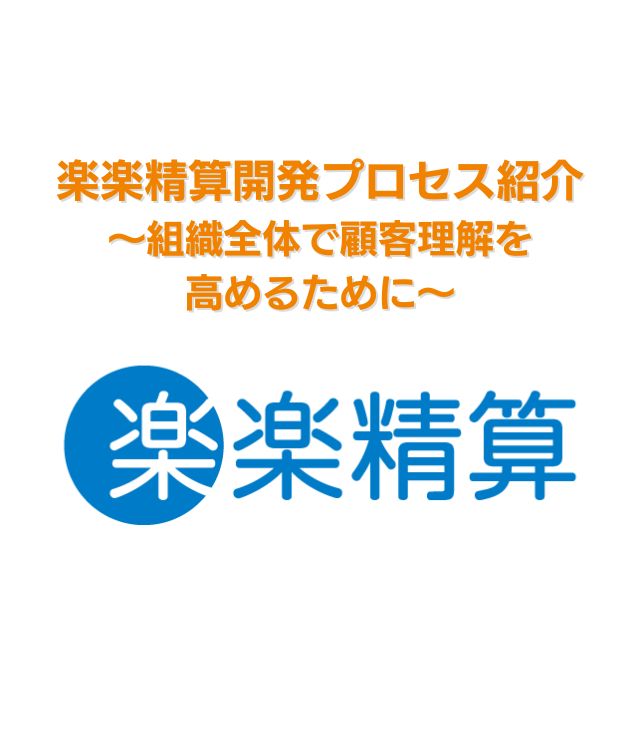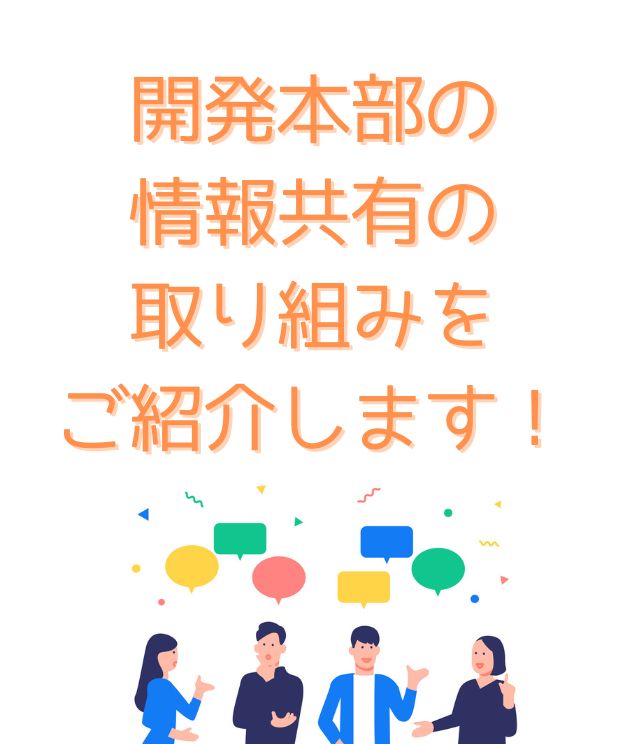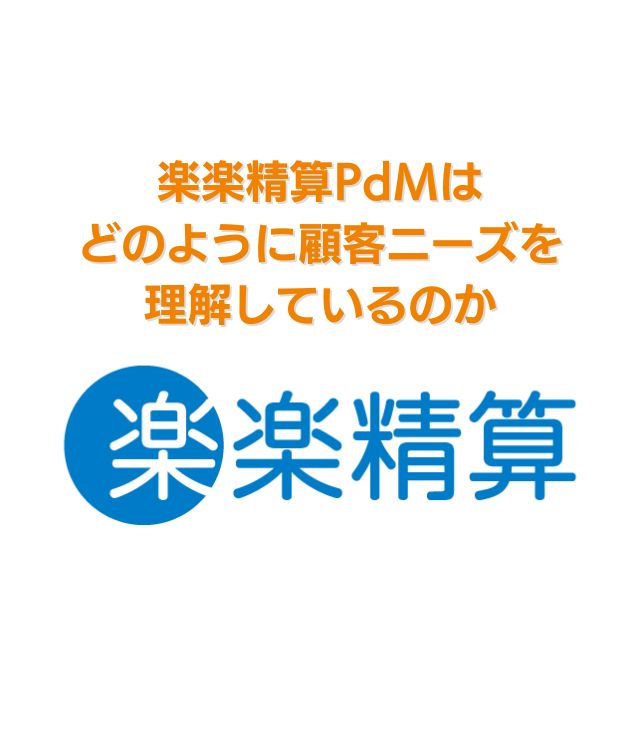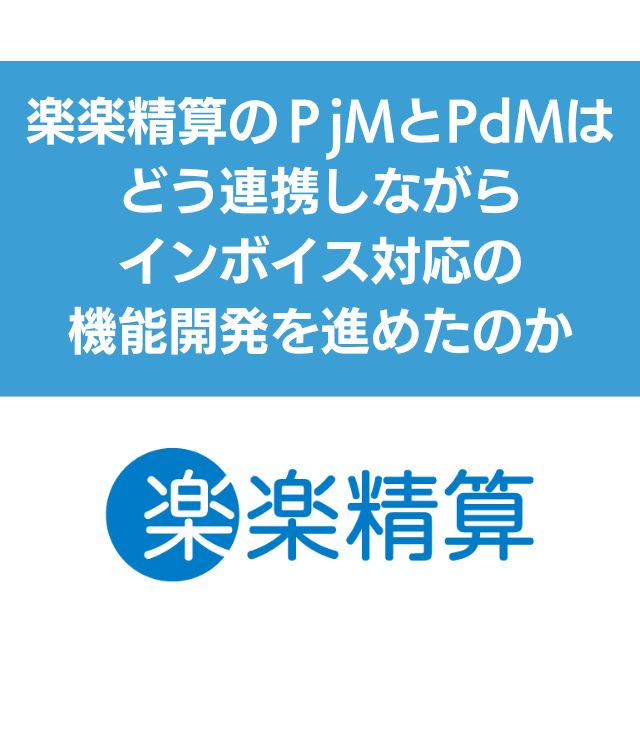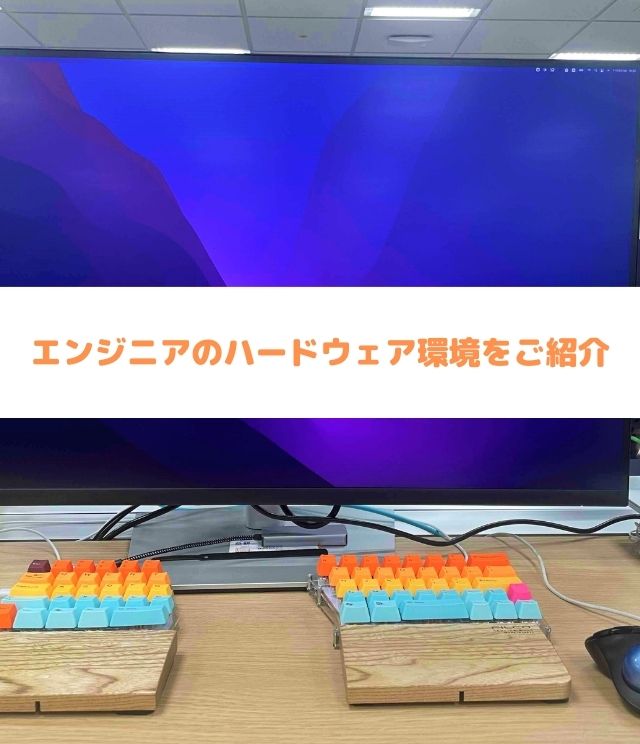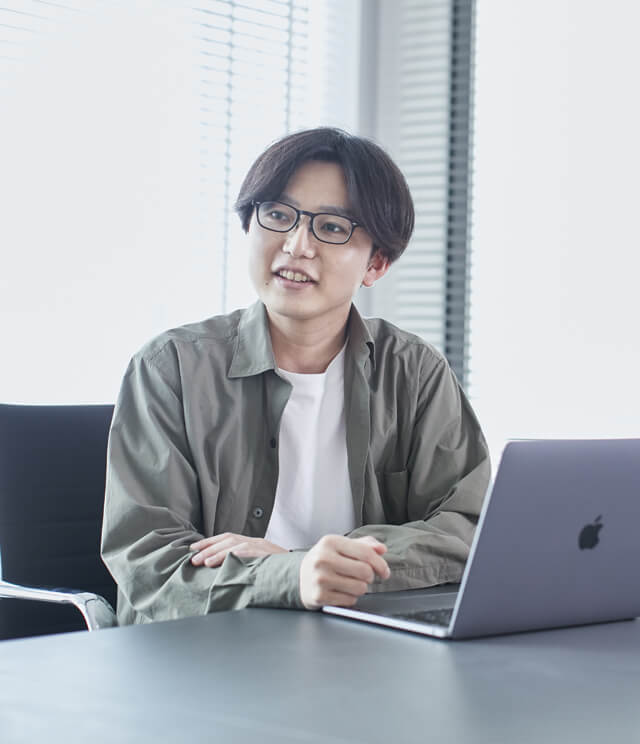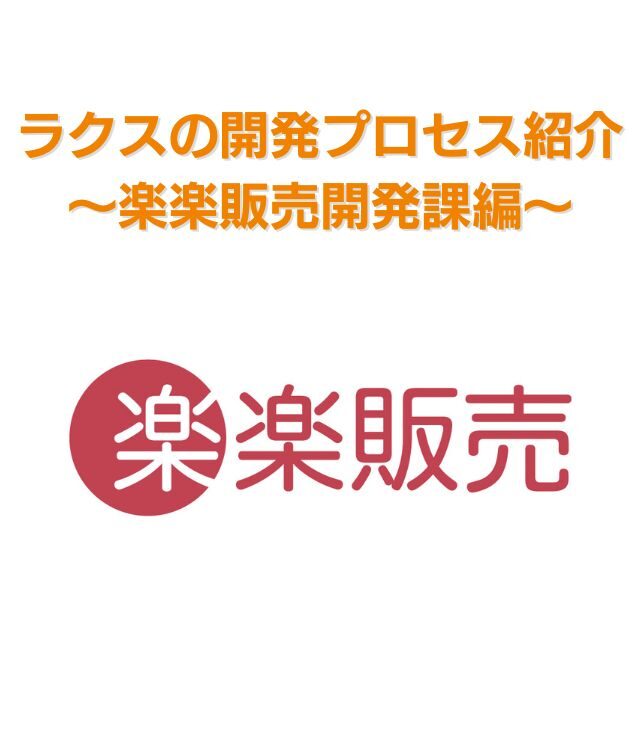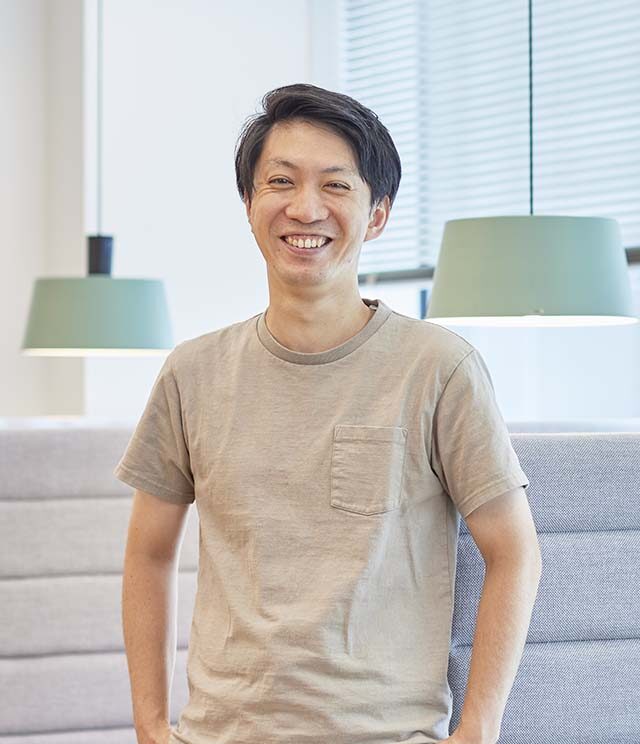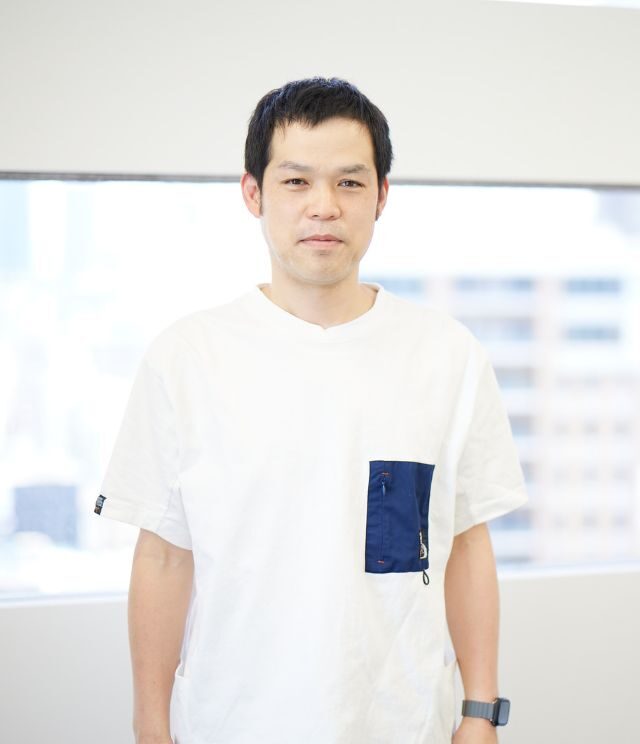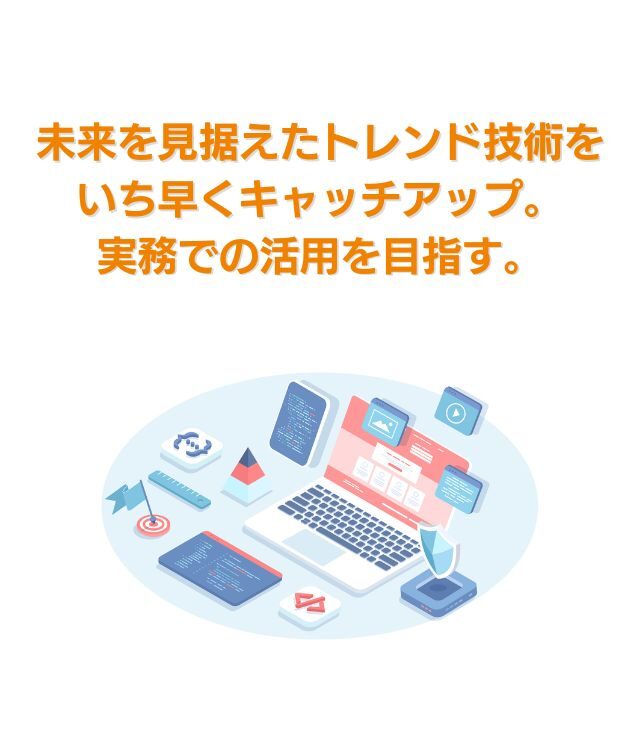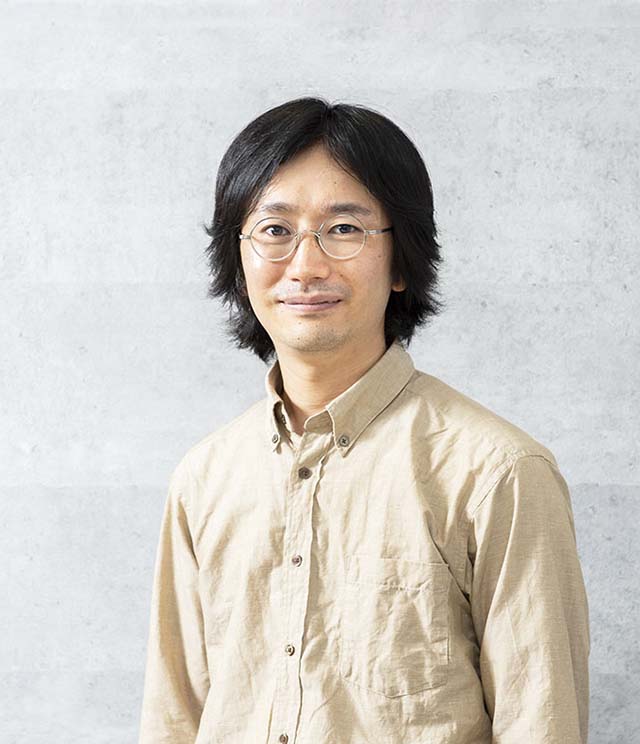PROFILE
小林 侑太
コーポレートIT統括部 業務システム部 部長
大学卒業後、ITコンサルタントとして7年勤務し、ERPソフトウェアの導入・運用支援を担当。2021年11月にラクスに入社。業務システム課の立ち上げから参画し、社内販売管理システムの改善・運用を担う。ラクス全体のDXを推進する役割を担い、2025年4月には課から部へと昇格し、部長に就任。ラクスのカルチャーである「ゴールオリエンテッド」を重視しながら「なんのためにやるのか」を大事に各々が主体的に取り組むことができる組織づくりをめざす。
ラクス全体の生産性を高め、目に見えた財務成果をもたらす
業務システム部とは、どんな役割を担う部署なのですか?
業務システム部は、自社のITによる業務改善をリードすることによって、ラクスグループ全体の生産性向上を実現することをミッションとしています。
部内は、社内基幹システムの管理・運用・保守を通じて安定稼働を支える組織と、AI活用やデータ分析基盤の企画・推進を担う組織で構成されています。将来的には、AIやデータなどの組織を分離して新設し、これらの領域をより強化していく予定です。各チームが専門性を持ちつつも、密に連携し、課題解決に横断的に取り組んでいます。
ラクスでは業務生産性の向上とスピードアップを全社目標として掲げており、当部署はまさにその中心的な推進役を担っています。2025年4月には、経営層からの大きな期待を受け、従来の『課』から『業務システム部』へと組織を強化・拡大しました。
めざすゴールについては、どう見据えていますか?
DXによって個別業務の負荷を軽減すること自体が目的ではなく、その効果を具体的な組織の財務成果に結びつけることをめざしています。もちろん、業務負荷の軽減は非常に重要です。しかしそれは、より付加価値の高い業務に挑戦するための『土台作り』と捉えています。社員が本来の実力を発揮できる時間を生み出し、会社の成長に直接貢献してもらう。そこまで繋げて初めて意味があると考えています。
その手段として有効なのがAIの活用です。既存業務をAIに置き換えることで、各プロダクトの新たな戦略や新プロダクトの立ち上げ、M&Aの促進など、新しい成長戦略に人的リソースを振り分ける余力を生み、事業成長=明確な財務成果につなげていきたいと考えています。

AIとデータで現場を変革:準備時間1/3削減を実現した生成AI活用事例
例えば、どんなプロジェクトに取り組んでいますか?
プロジェクトの例として営業部門におけるAI活用があります。
インサイドセールスやフィールドセールスといった営業部門では、商談前の顧客分析や資料準備に多くの時間が割かれていました。営業職の皆さんは、お客様への架電や商材の提案・デモンストレーションを行う際には、事前にお客様の企業情報やトピック、ラクス内の事例などを参考資料として用意し、準備しています。しかし、この準備作業に時間と労力がかかり、お客様と向き合う時間が圧迫されるという課題がありました。
そこで生成AIを活用し、外部情報と社内の導入事例を自動で収集・分析して、顧客の企業分析レポートを出力する仕組みを構築しました。一部の事業から先行して運用を開始しています。
営業現場からの評価はいかがでしょうか?
ある事業部でのトライアルでは「商談準備の時間が3分の1になった」という定量的な成果事例が出ています。他の事業部からも導入したいという声があがっており、利用部門を広げています。
他にはどんな取り組みを進めていますか?
全社的なデータ活用文化をさらに進化させるため、データ分析基盤の展開を進めています。
ラクスには元々データを活用する文化があり、社員それぞれが基幹システムのデータを分析・活用するということが日常的に行われていました。
しかし分析作業においては、各社員が基幹システムからデータをダウンロードし、手元のExcelで個別に集計・分析していたため、分析業務の属人化が課題でした。
このような課題に対して、当部署ではデータ分析を効率的に実施・共有するためのデータ基盤を整備・構築し、データ分析業務の改善を図っています。基盤の活用によって、ユーザーが必要とするデータをスピーディーに提供することに貢献しています。
最近ではデータ基盤においても生成AIの活用を進めており、自然言語での問い合わせを可能にするなど、データのさらなる活用を推進する基盤づくりを進めています。
この基盤は、先ほどのAI活用事例においても利用しており、それぞれの取り組みが相乗効果を生む状況となっています。
ラクスの社員=ユーザーの改善意識についてはどう感じていますか?
ラクスに入社した当初から感じていたのですが、ラクスの社員の皆さんは業務改善やIT活用に対する意識が高く、AIについても積極的に業務に取り入れてくれています。こちらから一方的に改善を促すというより、現場の皆さんから『もっと良くしたい』という熱量が自然と湧き上がってくるんです。その熱量に応え、さらに加速させていくのが私たちの役割だと感じています。
そういった要望のなか、当部署ではAIの活用をより力強く推進できるよう、社内専用のAIポータルサイトを立ち上げ、AIに関するトピックやノウハウ、社内における先行事例、プロジェクトの動きなど、さまざまな情報を週1回以上の頻度で更新・発信しています。
加えて、社員が自由に参加できるチャットグループをつくり、社員間でAIの活用事例や業務改善の成果、要望などを共有できる場もつくって運営しています。グループといっても全社員の半数以上が入っている規模で、やりとりがとても活発。中村社長も頻繁にコメントして、AI活用の機運を高めてくれています。
全社挙げて、という感じですね。会社としてITへの投資も積極的なのですか?
はい、AI技術の導入には非常に積極的です。健全な財務基盤を活かし、生成AIへの投資を重点的に行っています。例えば、全社員がGoogleのAIサービスであるGeminiのビジネス版を利用できる環境を整備しております。また、生成AIブームの火付け役となったChatGPTについても、ビジネス版のリリース後すぐに導入を決定するなど、常に最先端技術の導入に意欲的です。
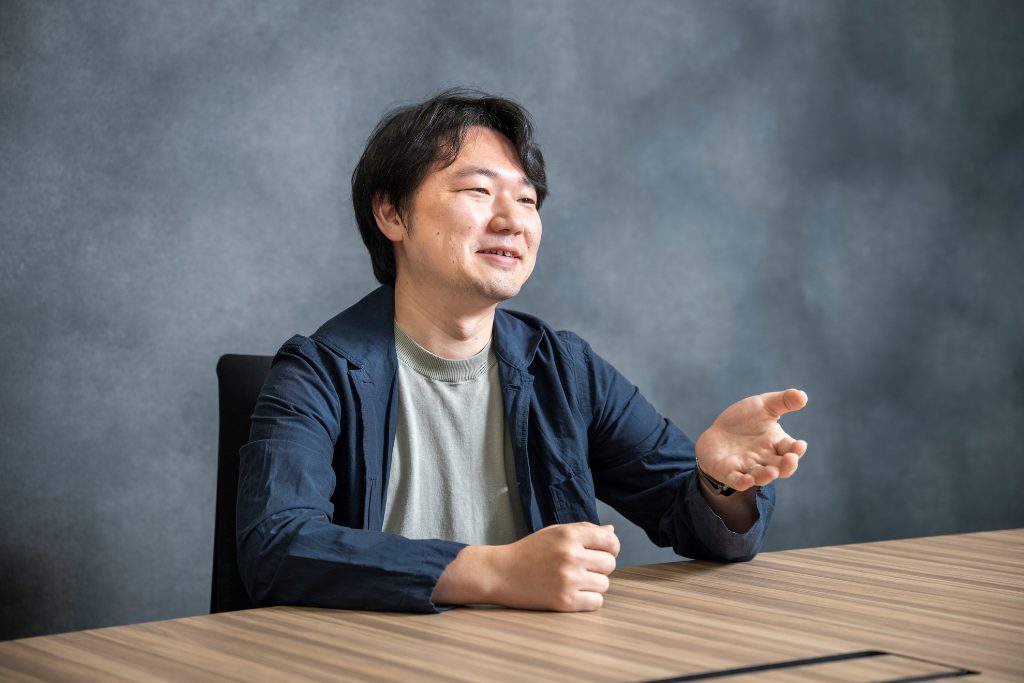
メンバーにプロセス全般の裁量を託し、スピーディに具現化
ITへの投資が活発で、導入の意思決定も速い。その起点となるのは、やはり現場の声?
そのとおりです。コーポレートIT統括部として、社員の皆さんからの要望や相談に応じる窓口を設けていて、「この業務を効率化したいけど、うまくいかない」「業務プロセスの改善について相談に乗ってほしい」など、さまざまな声が寄せられ、当部署のメンバーたちが随時対応しています。
しかし、個別の要望に応えるだけでは個別最適に留まるため、私たちは社員の声を踏まえつつ、全体最適の視点から各組織のメンバーやマネージャーと密に連携しています。それぞれの事業の戦略ゴール達成に向け、DX推進や新たなシステムの導入をプロジェクトとして推進しています。
多くの声が寄せられるということは、社内からの期待の表れでもありますね。
「これまでやりたくてもできなかったことが、効率化を図れたおかげでできるようになった」といった嬉しい言葉が社内から届きますし、ある事業責任者からは「事業戦略を考えるうえで、もはやデータ分析の基盤が欠かせなくなっている」という言葉もいただきました。
課題に対しては、メンバーそれぞれが対応しているのですか?
そうです。各メンバーが各組織からヒアリングした課題や要望をもとに、課題とゴールを設定し、要件を整理します。内製で開発しているのでスピーディに実装・運用まで至っています。
そして、その自律的な動きを支えるのが私たちマネージャー陣です。 メンバーの裁量とスピード感を最大限に活かせる環境を整えることを役割とし、日々のプロセスを細かく管理するのではなく、プロジェクトの目的やゴールといった大局的な視点でのすり合わせを重視しています。その上で、実行フェーズではメンバーの良き『壁打ち相手』となるなど、自律的な判断を後押しするサポートに徹しています。
個を尊重しながら、メンバー間・チーム間の連携も活発?
はい、連携が日に日に高まっています。
AIをはじめ新しいテクノロジーが増え、各組織の業務課題も複雑化するなか、難易度の高い要望に対してもスピーディに対応するためには、どのようなテクノロジーを使ってどう解決するか、チームのノウハウを結集して挑むことが欠かせないからです。
ときには一つの課題に対して複数のソリューション案がメンバーたちから提案され、その中から最適解を検討して進めるという組織プレーも見られます。また、現場との信頼関係構築のため、チームメンバー複数で支援にあたる、相談窓口を増やすなどの工夫も行っています。業務システム部のメンバーには相手の役に立ちたいという意識を持つ人が多く、親身な対応を心がけていますね。頼もしい限りです。

それぞれが自らゴールを設定し、主体的に動ける組織へ
業務システム部に加わることで、どんな成長を描けますか?
技術面では、クラウド上でのデータ分析基盤構築、生成AIを活用した業務自動化など、需要の高い技術を実務で深く経験できます。
ビジネス面では、単にシステムを導入するのではなく、「ゴールオリエンテッド」な思考をもとにした課題解決力が身につきます。ラクスのカルチャーでもあるゴールオリエンテッドとは、まず『あるべき姿=ゴール』を設定し、そこから逆算して『今やるべきことは何か』という課題を見つけ出し、実行する姿勢のことです。そして、その計画がゴールに繋がっているかを常に問いかけ、必要であれば柔軟に軌道修正を行なっていきます。
『IT業界あるある』とも言えることだと思うのですが、依頼通りにシステムやアプリケーションを開発しても、実際にほとんど使われないケースが少なくありません。
ラクスでは、まさにそうした非生産的な状況を生まないために、ゴールオリエンテッドの考え方が活きてきます。メンバーが自らゴールを描き、どうすれば本質的な課題解決に繋がるかを考え抜く。このスタンスを当たり前のものとして実践し、習得できることも、ラクスで働くメリットだと思います。
では、組織としてめざす姿は?
やはりベースとなるのはゴールオリエンテッドです。メンバーそれぞれが組織のゴール・課題への理解を深め、自分に何ができるかを考え、行動すること、それを安定的に実践できる組織でありたいと思っています。そうなることが、ひいてはラクスグループ全体への貢献につながると考えています。
実際にわたし自身も、組織レベルでのミッション・ビジョン・戦略ゴールの策定が求められ、組織として何をすべきか、何に貢献すべきかを強く意識するようになり、組織運営や方向性を考えることが自身の成長に繋がっていると感じています。自身でゴールを設定し、貢献できる領域を広げていく考え方は、以前の自分にはなかったものであり、マネジメントにおいても重要な要素になっています。この考え方を今後も組織に反映していきたいと考えています。
最後に、ラクスへの入社を検討中の皆さんへメッセージをお願いします。
改善への意識が高く、自ら主体的に考え、行動に移せる方を歓迎します。
業務システム部の「部」としての活動は始まったばかりで、成長フェーズにある組織です。そのため、完成された組織に加わるのではなく、自分たちの手で組織文化や仕組みを創り上げていく面白さを実感できます。今後、内部でのリーダー層の育成はもちろんのこと、ハイレイヤー層の採用も積極的に進め、多様なバックグラウンドを持つリーダーを迎え入れることで、業務システム部をさらに強固な組織へと発展させていきたいと考えています。組織内でポジションが増えていくフェーズですから、キャリアアップの機会も豊富です。
これからのラクスを支えるDX組織を、中心メンバーとして一緒に創り上げていきましょう。
※所属・役職はインタビュー時点(2025年6月)のものです。