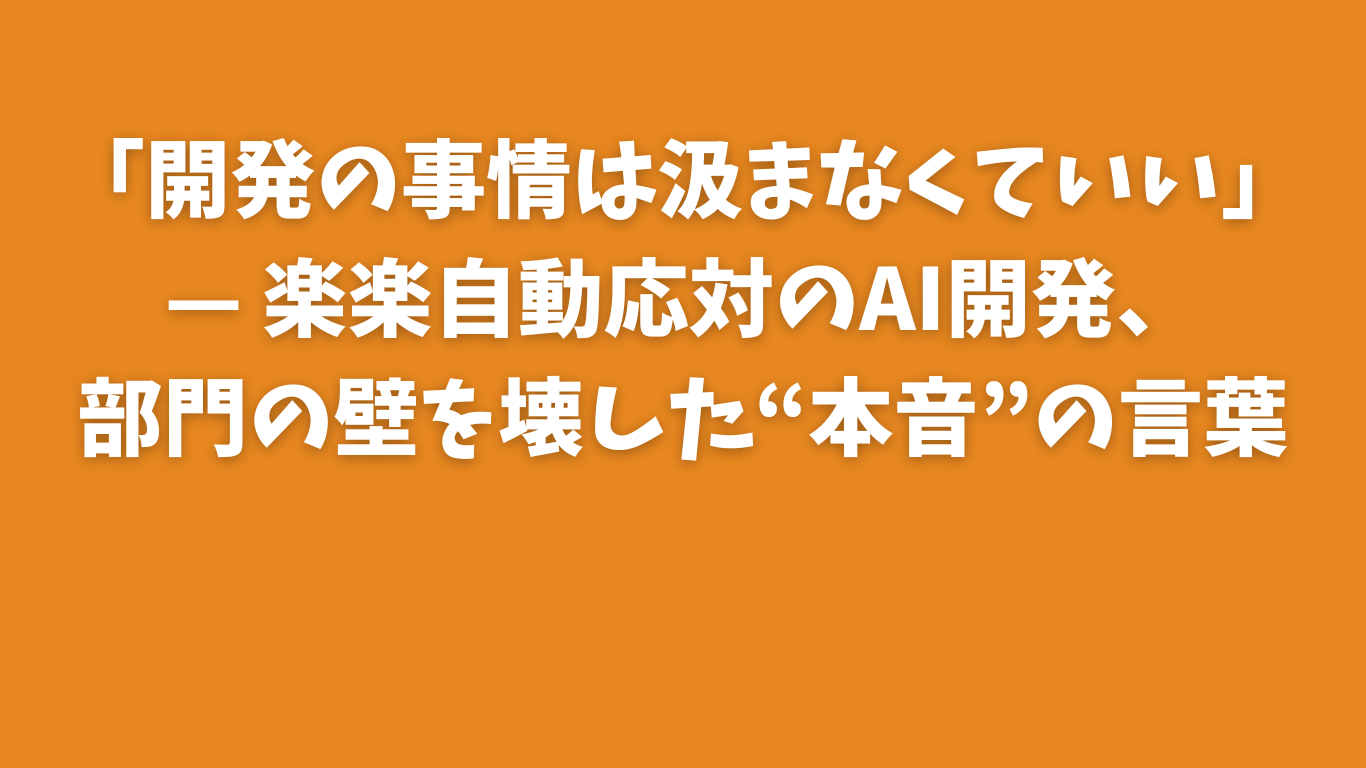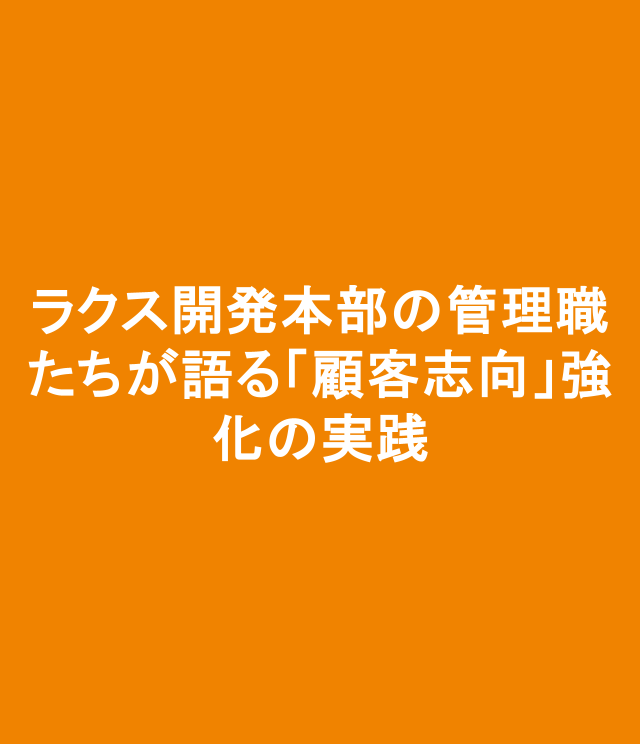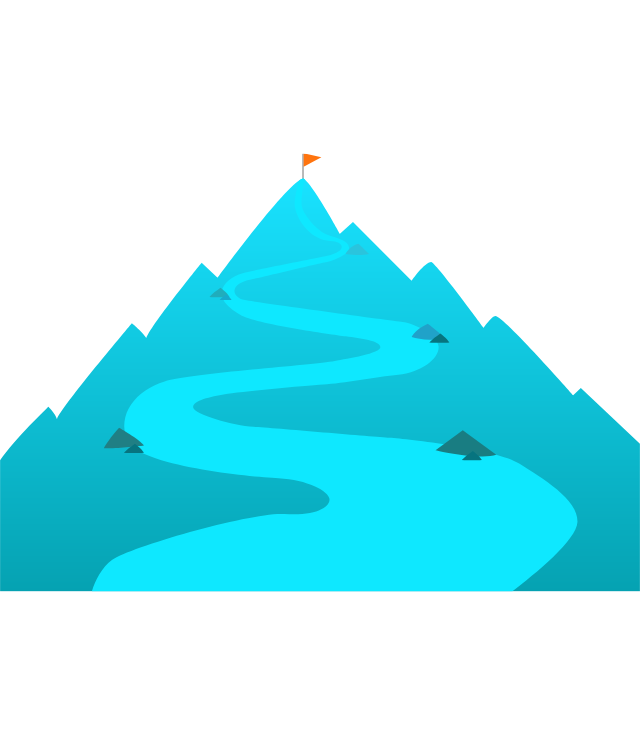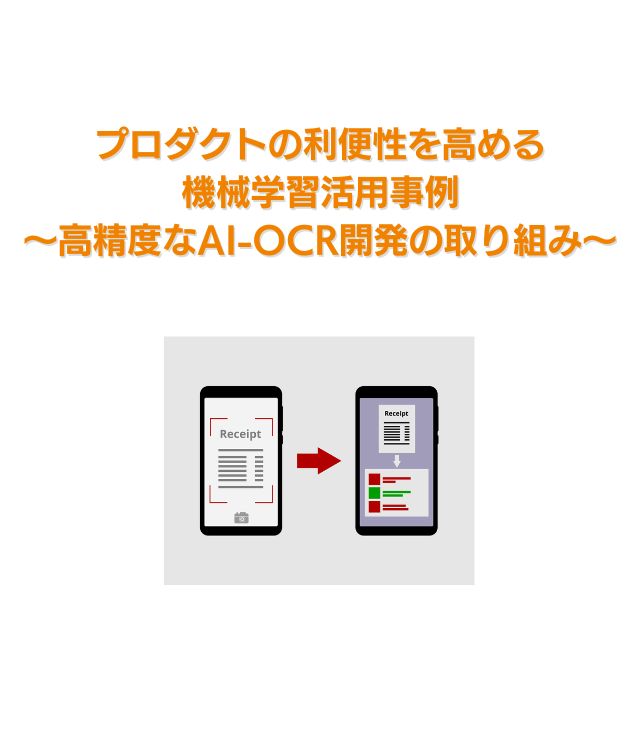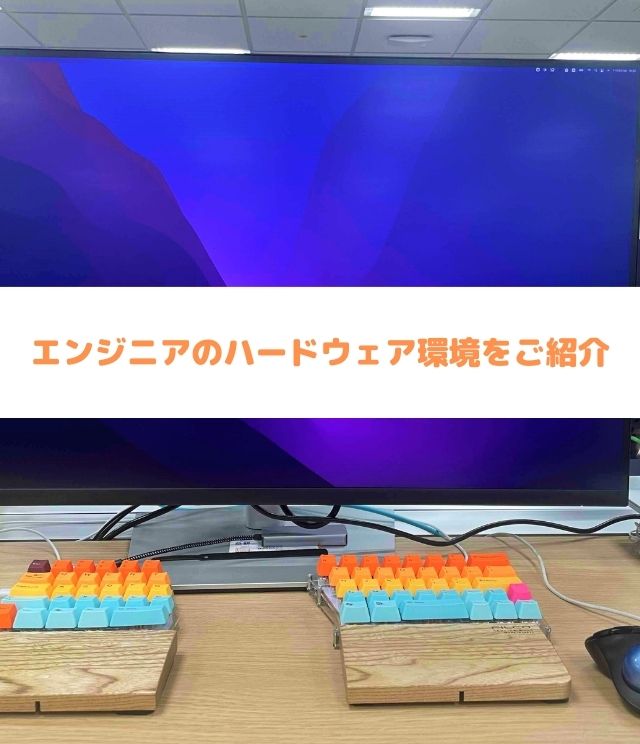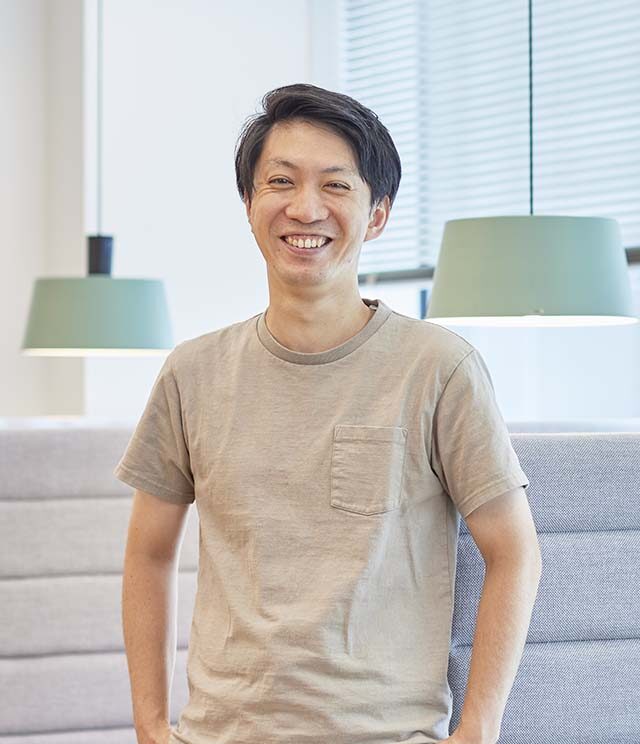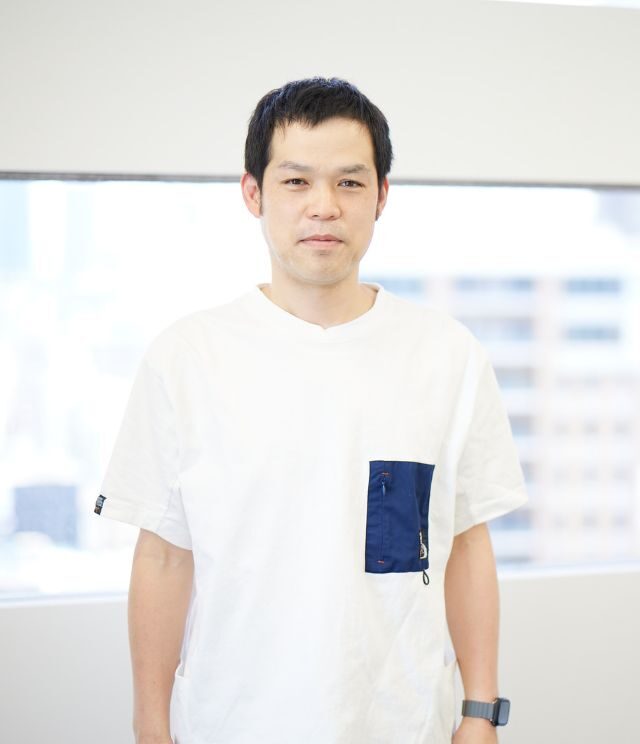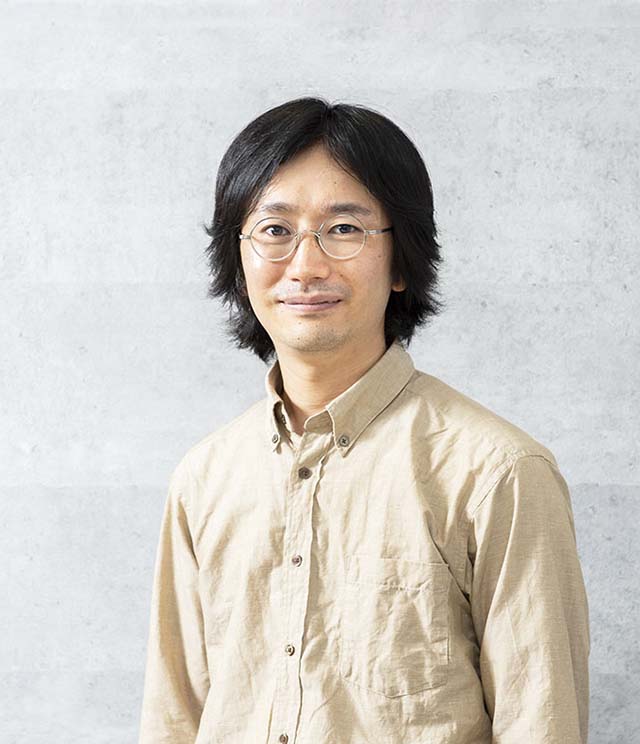PROFILE
髙嶋 洋
ラクスクラウド事業本部 戦略企画部 副部長
楽楽自動応対(旧名称:メールディーラー)と楽楽メールマーケティング(旧名称:配配メール)の製品・営業・CS戦略の企画実行を管理。
「このままだと、楽楽自動応対はディスラプト(破壊)される」
経営陣から放たれた一言が、チームの空気を一変させました。 Netflixがレンタルビデオ店を過去のものにしたように、生成AIの波は、私たちのプロダクトの価値を根本から覆す可能性を秘めています。
ラクスの創業期から顧客のビジネスを支えてきた主力製品『楽楽自動応対(旧名称:メールディーラー)』。 「安定した製品」というレッテルを剥がし、AIという未知の領域へ踏み出した開発チーム。そこにあったのは、「ビジネスサイド vs 開発サイド」の対立ではなく、職種の壁を越えた“本音の共闘”でした。
なぜラクスは、トップシェア製品の在り方を根本から変えるような挑戦ができたのか。エンジニアたちが口にした驚きの言葉とともに、その裏側に迫ります。
「顧客にメールが来なくなる未来」への危機感
「正直、AIはラクスにとって難しいテーマでした」 戦略企画部門で製品戦略を担う高嶋さんは、当時の葛藤をそう振り返ります。
ラクスには「成果が出るものに絞る」という堅実な文化があります。しかし、生成AIはまだ費用対効果が見えにくい。お客様からも「AIが欲しい」という声はあるものの、具体的にお金を払う段階ではありませんでした。
しかし、経営陣の「ディスラプト」発言が状況を変えます。 チームが突き詰めたのは、楽楽自動応対の契約が0件になる最悪のシナリオ。
高嶋さん: 「AIチャットボットが完璧になれば、人間への問い合わせは激減します。つまり『お客様にメールが来なくなる』未来です。その時、メール管理システムである私たちの製品は価値を失う。このリスクを前に、悠長なことは言っていられませんでした」
顧客自身も「AIで何ができるか」の正解を持っていない中、チームが出した結論は一つ。 「問い合わせの上流に踏み込み、問い合わせが生まれる前の段階からお客様を助ける」こと。 この構想を実現するため、前例のないスピードでの「AI機能早期リリース」が絶対条件となりました。

エンジニアが放った一言。「ラクス対世界なんだから」
戦略企画の高嶋さんは、開発チームに早期リリースのロードマップを提示しました。それは、通常のアジャイル開発のサイクルすら凌駕する、無理を承知の打診でした。
「開発リソースが足りない」「技術的な負債が」——そんな反論を覚悟していた高嶋さんに対し、開発統括部のエンジニアリングマネージャーから返ってきたのは、想像を超える言葉でした。
「開発の事情は汲まなくていい。ビジネス的にいつ欲しいのか、本音を言ってください。社内で忖度している場合ではない。もはや『ラクス対世界』という状況なんだから」
社内の調整やリソースの言い訳よりも、「市場で勝てるかどうか」を最優先にする。 この言葉により、ビジネスサイドと開発サイドの間にあった「依頼する側/される側」の壁は消滅しました。
高嶋さん:「これまでのルールがある中で、開発側からそう言ってもらえるとは……。部門を超えて、全員が『顧客と市場』という同じ方向を向けた瞬間でした」
高速な仮説検証。「きれいなコード」より「動く価値」を
前代未聞のミッションに対し、開発現場はどう動いたのか。PdMと、実装を担当した開発エンジニアにお話を聞きました。
── 開発側から「もっと早くできる」と提案したと聞きました。
PdM Kさん: 「危機感ですね。展示会で他社のAIエージェントを見た時、ラクスがそこにいないことに『これはまずい』と肌で感じました。現場の課題解決はもちろんですが、それ以上に市場から置いていかれることへの焦りが原動力になりました」
── 具体的にどうやって開発スピードを上げたのですか?
PdM Kさん: 「徹底した『高速な仮説検証』です。とにかく早く『見えるもの』を作る。 例えばサジェスト機能のプロトタイプは、TampermonkeyのスクリプトをAIに書かせて、ペラ1枚の画像でもいいから動くものを作りました。要求定義書をこねくり回す時間を削り、動くものを提示して認識を揃える。エンジニア主導でこのプロセスを回せたことが勝因です」
── 現場への負担も大きかったのでは?
開発エンジニア Hさん: 「正直、ハードワークな時期もありました(笑)。でも、それは『上から降ってきた無理難題』ではなく、『この波に乗るなら今しかない』という納得感があったからです。 会社全体が本気でAIに舵を切っている熱量を感じていましたし、エンジニアとして新しい技術でプロダクトが変わっていく過程は、純粋に面白いものでした」
── 開発者として、一番の手応えは?
開発エンジニア Hさん: 「社内のCS(カスタマーサポート)から『クレーム検知機能のおかげで早期介入できて助かった』と言われた時ですね。自分たちが作ったコードが、誰かの仕事を確実に救っている。『使われている』という実感と喜びは、何物にも代えがたいです」
「顧客志向」は、開発の現場でこそ試される
チームの奮闘は、やがて「顧客との共創」へと繋がりました。 ある顧客へのヒアリングで、こんな言葉をかけられたのです。
「楽楽自動応対と一緒に、AI機能を作っていきたい」
「お客様に聞いても答えはない」と考えていたチームが、自ら未来を提示したことで、顧客がパートナーになってくれた瞬間でした。
最後に、今回のプロジェクトを牽引した2人からのメッセージです。
戦略企画・高嶋さん: 「このプロジェクトで感動したのは、開発チームが『社内』よりも『世間やお客様』の方を向いてくれていたことです。議論の中に『技術的にできない』という言葉は登場せず、常に『どうすれば実現できるか』という前向きな議論ができた。変化を恐れず一緒に走れるエンジニアチームを誇りに思います」
PdM Kさん: 「私たちは単にコードを書いているわけではなく、『ラクスの看板』を背負って市場と戦っています。 一番歴史の長いサービスである楽楽自動応対が、AIによって進化する。これは『レガシーな製品でも、エンジニア次第でいくらでも新しくなれる』という証明です。顧客のために技術を使いたい人にとって、これほど面白い環境はないと思います」
ラクスでは、共に「未来」を実装する仲間を募集しています
「開発の事情は汲まなくていい」 この言葉は、エンジニア軽視ではなく、エンジニアとしての強烈な自負とプロフェッショナリズムから生まれたものでした。
言われたものを作るのではなく、ビジネスサイドと対等なパートナーとして、顧客の未来を創る。 そんな環境で、あなたの技術力を発揮してみませんか?